かわいらしくおいしそうな作品には熱狂的にファンも多い、お菓子作家efuca.イトウユカさんの、全部お菓子でできた探し絵えほん『さがそ!おかしのくに』シリーズが、大好評につき第三弾の登場です。エフカちゃんとネコのフーガちゃんは今度は世界旅行に出発!
応募締切)3月14日(月)
※発送をもって発表に代えさせていただきます
****************
efuca.イトウユカ著
『さがそ! ~おかしのくに せかいりょこう~ 』(学研教育みらい)
定価)本体1,300円+税/A4変型・本文32ページ
書籍の紹介はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
最新記事を毎週配信
ご登録はこちらから↓



![『さがそ!~おかしのくに せかいりょこう~』プレゼント![締切:3/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/73dacc5e12caa7fe6c6b3a53e6afb619-730x510.jpg)


![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第36回 [2/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/pixta_19967357_S-640x510.jpg)



![☆腸を元気にするおかず「蓮根のはちみつしょうゆ煮」[2/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/6f2d20e85fe329b9d5226171872a3b52-825x510.jpg)

![★正しい音程を身につけるための環境づくりって?[2/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/fb973a20079f73283d4e794936ef4d24.jpg)

![★給食を食べ残すのはなぜ?[2/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/1164a54fd6c2299ee29dbe9b68952506-825x510.jpg)


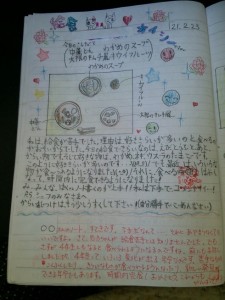
![★歌うとき、音がはずれるのは遺伝なの?[2/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/e3874d91227c348c871b0e6eede511411.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第35回 [2/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/20160215-640x510.jpg)

![☆子どもが親の言うことを聞かなくなるのはなぜ?[2/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/7e002d71e781686db8a0fa69936e361c.jpg)

![☆「失敗」を怖がって子どもを手助けしていませんか?[2/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/d596fee4a45aae7f51adf67696d9d961.jpg)

![☆腸を元気にするおかず「ベーコンと水菜の卯の花」[2/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/4460fa504b9bcf9b68d7bdfc6a1d906d-825x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第34回 [2/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/pixta_17127846_S-640x510.jpg)



![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第33回 [2/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/pixta_19696675_S.jpg)

![★レシピ本『LEOCのバランスごはん』をプレゼント![締切:2/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/51dE0i0m0-L.jpg)
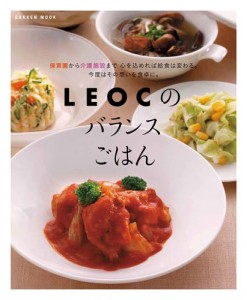
![☆パパが育児に協力的になる3つ の方法[1/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/211e22f9389dd159010586396f90bde5.jpg)

![★扁桃腺は、取っても大丈夫?[1/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/76328d4aa9cbaf41deab03a9496dce03-640x510.jpg)

![★扁桃腺が腫れやすいのはなぜ?[1/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/4634af467744b45729670c6cfe6983f9-582x510.jpg)

![★扁桃腺が腫れたら、どうすればいい?[1/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/325fd3fd529cc08e8c0d7f650febc8de-413x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第32回 [1/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/pixta_6631549_S.jpg)

![★3世代の話題にいかが? 昭和〜平成の給食ストーリー その2[1/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/2f6ed6318a37afb084f508071a67ae1d.jpg)






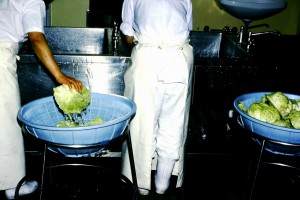



![★子どもの連れ去りに注意! 不審者の声かけパターン[2016/4/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/7f8ecb3f4df14caf24b3a1e6ce854709.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第31回 [1/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/pixta_11854569_S-627x510.jpg)



![★3世代の話題にいかが? 昭和〜平成の給食ストーリー その1[1/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/2615fd2a25c9aac11d4605b2d911b320.jpg)

![☆『ママノートダイアリー2016』をプレゼント![締切:2/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/bb6756eaf599d90fbba049cc5eb2aa69-755x510.jpg)
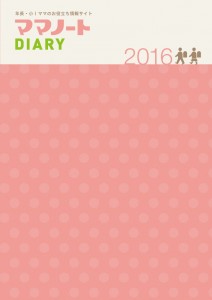
![☆風邪を早く治すにはどうすればいいの?[1/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/18b38de5370b8d0290417520a24bcdf0.jpg)

![★「スマホの動画・ゲーム」家庭ルールのポイントは?[1/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/12/ddab5f19669bbecd4bc8fe029b7d7026.jpg)

![☆「風邪をひきにくい子」にさせる方法とは?[1/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/01/3c0d95cc2288a6fd703391bc16694a2d.jpg)
