こんにちは、現役小学校教員の舟山由美子です。
お子さんが学校でひとりで過ごすことが多いと聞くと、心配する親御さんがほとんどです。ひとりでいることが好きな子に対して、大人は「ひとりぼっち」「友だちがいない」という見方をしてしまいがちですが、はたして本当にそうなのでしょうか。
Q.ひとりが好きな子、もう少し社交的になってほしい
うちの子はひとりでいるのが好きなタイプで、休み時間なども放っておくと1人でいるそうで、特に仲のいい友だちもいないようです。
担任の先生からは「よく周りが見えているし、自分できちんと考えて行動できるということです。個性と考えて気にしないほうがいいと思います」と言われましたが、親としては心配です。嫌がられるとわかっていても「今日は誰と遊んだの?」などとしょっちゅう聞いてしまいます。
もともとそれほど社交的ではありませんでしたが、だんだん友だちもできてくるだろうと心配していませんでした。でも4月からは3年生なので、「このままでいいのかな?」と思うようになってきました。もう少し社交的になるために親ができることはあるでしょうか?
(ペンネーム みろたん)
A.「あるべき枠」にあてはめずに子どもを見守りましょう
ご相談文からは、兄弟姉妹がいるかどうかわからなかったのですが、お子さんは一人っ子でしょうか。小学校入学前からそんな感じであったということですね。きっとお母さんご自身は、友だちと一緒にいることが多いお子さんだったのですね。
実は、この相談コーナーを担当させてもらっていると不思議なことがあるのです。
今まさに読んでいる本や、記事や、見たテレビ番組が、あるいは自分のクラスで抱えている問題・課題が、そのときにいただいている相談に対する答えのようなものになるのです。
これは「共時性」というらしいのです。きっと無意識のうちに関連した事項を探しているからかもしれないのですが、相談文を読ませていただく数日前から手に取って読んでいた本の中に、私の回答の指針が示されているように感じることがあるのです。
読んでいた本は、岩波ジュニア新書『大人になるっておもしろい?』(清水真砂子著)で、著者は『ゲド戦記』の翻訳も手がけた児童文学者です。
児童・生徒(特に思春期と呼ばれる人)に対して、「怒れ! 怒れ!」と応援したり、けんかってそんなにいけないことなのだろうかと問うたり、「ごめんね」「いいよ」の氾濫(はんらん)(保育園・幼稚園や小学校でよく行われること)の気味悪さを語ったり、生意気っていけないことなのか、「沈黙」も表現である……などと綴っています。
その中で「ひとりでいるっていけないこと?」という章があります。
まさに、ご相談者のお悩みです。興味がわいたようでしたら、ぜひそれを読んでいただいたほうが早いのですが、要約すると、著者の言葉でいうところの「独り居(ひとりい)」でいることで自分自身の内なる心の声に耳を澄ますことができるし、ひとりになるのを恐れ恥じてグループにつこうとするとき、自分の内側の声にふたをしてしまうことがある、と言うのです。
『ベーグル・チームの作戦』というアメリカの児童書の引用として「成長のほんの一部分だけが、みんなの前と家族の前で起こる。あとの大部分がひとりでいるときに起こる」ともあります。そして同時に読書の森に分け入る価値も語っています。
親も教師も子どもに対しては、「あるべき枠」をはめてしまいがちだとおっしゃりたいのだと思いました。
今、ほとんどの小学校の教員は、ひとりでいる児童に「みんなと一緒に遊んで来たら?」と言うと思います。子どもは元気で外遊び!という「枠」をもっているからです。そう考えると、お子さんの担任の先生は、娘さんのことをよく見ておられると感じました。
私はよく子どもたちに、「仲がよいのと、群れているのとは全然違う」と言います。
相談者のお子さんは、群れるのが嫌なのかもしれません。本を自分のペースで読んだり、ひとりでいたりするときのほうが、みんなでいるときよりもたくさんの言葉が浮かんでいるのかもしれませんね。
お母さんは、「今日は誰と遊んだの?」と尋ねるのではなく、「学校でどんなことを考えているの?」「どんな本を読んでいるの?」と尋ねてみてはどうでしょうか。もしかすると、お母さんがもっている「枠」をはるかに越えるものを持っているお子さんかもしれません。
そんなお子さんには、数は少なくても、同じ価値観をもった友だちができると思います。
それは3年生のときかもしれないし、そのずっとあとなのかもしれませんが、担任の先生がおっしゃった「よく周りが見えているし、自分できちんと考えて行動できる」子という見立てを信じてよいのではないでしょうか。
舟山先生のほかの記事はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓






![★登校班をよりよくするためには?[2016/4/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/d17e1921c5d9240292fd913eaba2362d1-640x510.jpg)

![☆学童保育を上手に利用して「小1の壁」を乗り越えよう[2016/4/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/10/20160405.jpg)

![☆毎日30分、机に向かうことから「学習習慣」をつけて[2016/4/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/10/20160406.jpg)

![★『知ってたのしい みぢかなぎもん』プレゼント![締切:2016/4/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/4052044142.jpg)
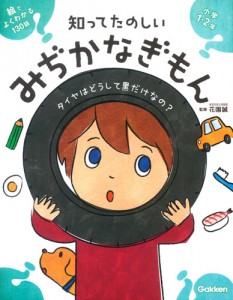
![★親野智可等の「ママも小学1年生」第1回[2016/4/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/04/20160404-640x510.jpg)

![☆[入学準備] 入学後に、働くママが悩む「小1の壁」[2016/4/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/68d3ec36cdea4dc49d732051f9e12d90.jpg)
![☆入学後の子どもの変化を見逃さないで[2016/4/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/10/20160404_2.jpg)

![☆[入学準備] 新1年生、入学後の1日の過ごし方[3/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/nyugaku.php_.jpg)
![☆[入学準備] 入学後に幼稚園ママの生活はどうなる?[3/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/mama07.php_.jpg)
![☆[入学準備] 入学式に持っていくと便利なものは?[3/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/0954_img_01-650x510.jpg)

![☆友だちづき合いが上手な子になる3つの方法[3/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/7a9dbe6cf05ac17ea0d9ff4e6dffba19.jpg)

![☆これはNG! 子どもが心を閉ざす親の言葉[3/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/60b0b8586cd5e718b853aa4cb41d13f2.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第40回[3/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/pixta_18383353_S-640x510.jpg)

![☆簡単! 魚おかず「ぶりとしめじの生姜風味あんかけ」[3/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/6e30db68562b37413593a51258dbff8e-825x510.jpg)

![☆体を動かす遊びが「キレにくい子」を育む[3/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/322d95ef44940950ff46a975eb634d0b.jpg)

![☆「キレやすい子」と「キレにくい子」の違いは何?[3/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/81b3e99e2e3e7150aa55a8038e77c05b.jpg)



![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第39回 [3/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/pixta_9424559_S.jpg)

![★「ママ名刺」を活用すれば友達がたくさんできる![3/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/d56634a0ccd21e3810a81eb9f330910f.jpg)

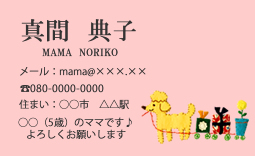
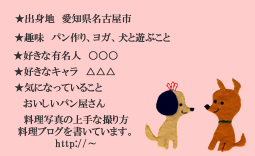
![☆『新版・ふれあいしぜん図鑑 春』プレゼント![締切:4/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/4052041356.jpg)
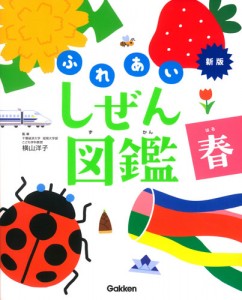
![★「ママ友」トラブルはこわくない?[3/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/f38265f1b034e64be4c9fdc055a87a00.jpg)

![☆1年で食べることへの意欲が育ちます![3/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/38b3c332c92325fd1d261a4e5e8b41ec-825x510.jpg)

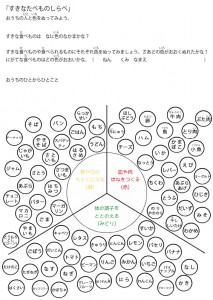
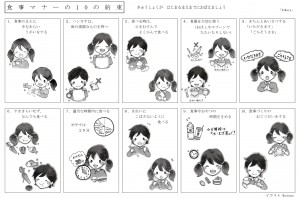
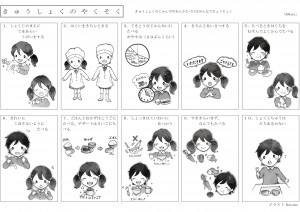
![★ママ友関係で孤独にならないためにできることは?[3/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/587f7d852f1253c2e06546374dc2500f.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第38回[3/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/pixta_14397431_S.jpg)

![☆魚おかずで脳を活性化「鮭と白菜の和風クリーム煮」[3/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/03/4589e308d4999c0dbaca7205bf8bce87-825x510.jpg)



![☆[入学準備]入学前に、生活リズムを整えよう!](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/527dd1102b5544cded45ac9600b134d0-640x510.jpg)

![☆ゲームの時間の約束が守れる子になる3つの方法[2/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/aa7ad91a4a40ad5ca1ec3a3fbb5637a2.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第37回 [2/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/02/pixta_12708844_S.jpg)
