前回は、子どもを「甘えさせる」ことの大切さについて、ライフ・カウンセラーの三浦久美子先生にうかがいました。
毎日の生活の中で、「甘えさせ」なのか「甘やかし」なのか、迷う場面はたくさんあるのではないでしょうか。
今回からの2回は、お母さんたちが迷うケースを取り上げ、どんな場合が「甘えさせ」あるいは「甘やかし」なのか、三浦先生にお話をうかがいながら考えていきましょう。
●電車の中でお菓子をせがまれて与えるのは?
ケース1
電車の中で子どもが「おなかがすいた、お菓子を食べる」としつこく言ってきたとき、そろそろ公共でのマナーを教えたいけれど、大人の買い物に付き合わせたので疲れたのかなと考え、食べさせてしまいました(年長)。
三浦「厳密な意味では『甘えさせ』とは違うかもしれませんが、『甘やかし』ではなく、子どもの甘えを受け入れたと言っていいでしょう。
その理由は、結果的にお菓子を食べさせているけれど、『大人の買い物に付き合わせたので疲れたのかな』と、子どもの感情の意図や理由を考えて受け入れているからです。
これがもし、『しつこく言われてうるさいし面倒だから』食べさせたというのであれば、それは完全に『甘やかし』です。
『食べさせるという結果が一緒なのに、なぜ?』と思われるかもしれませんが、過程が違うことがポイント。子どもの甘えを受け入れたお母さんであれば、実際の場面では「疲れたよね。少しだけね」などと言ってあげていると思います。
でも『面倒だから』というお母さんの場合は、『もう〜、しつこいんだから、しょうがないわね!』と言っているのではないでしょうか。
これでは子どもは受け入れてもらったと感じることはできませんよね。むしろ『しつこく言えば、くれるんだ』と誤った学習をしてしまいます。
そして、このケースのお母さんの場合、『公共でのマナーを教えたい』ということですから、さらにもう一歩進んで、大人になっても通用するマナーを子どもに教える絶好のチャンスととらえ、この場面でやっていいこと・いけないことを子どもに教えましょう。
例えば、お菓子を際限なくボリボリはダメだけど飴ならOKとか、可能であれば一度電車を降りて、ホームで食べさせるとか、どうすれば公共のマナーとして許されるのか、お母さん自身が同じようにお腹がすいてがまんできないときにどうするかを考えてみてください。
●「ジュース飲みたい」と泣いてぐずる子どもの言うことをきくのは?
ケース2
夕食の支度をしていると、子どもが必ず「ジュースを飲みたい」とか、「これ見て、これ見て」などと、うるさく言ってきます。
忙しいので、「あとでね、ちょっと待ってて」と言うと泣いてぐずりはじめるので、結局いつも言うことを聞いてしまいます(年長)。
三浦「『泣いてぐずり始めるので』という言葉にあるように、お母さんが子どもに寄り添うのではなく、料理を邪魔されるのを回避するためにジュースをあげたり、言うことを聞いているので、これは『甘やかし』になると思います。
自分の要求が拒否されたわけですから、子どもが泣くのも無理はありません。
こういうとき、お母さんも忙しくてイライラしているでしょうから「あとでね、ちょっと待ってて」と言う口調も、優しい「ちょっと待っててね♡」ではなく、「ちょっと待ってなさい!(怒)」というニュアンスになっているのではないでしょうか。
実は、お母さんが忙しくて子どもの気持ちを受け入れる状態でない場合に、こういう要求がよく起こります。
つまりこれは「私いるよー」と言ってるようなもの。『ごめんね』と謝った後、『ご飯を作り終わったらね』などと、具体的な予測を立てられる言葉がけをするといいでしょう。
『ちょっと待ってて』では、あまりにも漠然としていて、子どもはいつまで待てばいいのかわかりません。
子どもがお母さんにかまってほしくて、いろいろ要求しているなと思ったら、まずとりあえず『なあに?』と言って、子どもに目を向けましょう。
『なあに?』の後、例えば子どもが『これ見て』と行ったら、『わあ、すごいね』などと返事をします。
『それでね……』と続くようであれば、そこで『ごめんね、ご飯を作り終わったら見せてね』と伝えればいいんです。これだけで、子どもは受け入れられたと感じられ、『しょうがないか』と気持ちを切り替えられるんです。
ここまでにかかる時間は、ものの10秒くらい。忙しいと、つい自分の感情に走ってしまいがちですが、実は子どもが受容感を感じられるようにするのに、それほど時間はかからないんですよ」
忙しいとイライラが先に立って、「子どもにていねいに接するなんてムリ!」と思っていましたが、そうではないんですね。
三浦先生、ありがとうございました。
次回も引き続き、お母さん方のケースと先生のアドバイスをご紹介します。
三浦先生の他記事はこちら
関連記事はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓
ツイッターもやっています!
フォローはこちらから↓



![☆これって、「甘えさせ」?「甘やかし」? 前編[6/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1045_img_01-300x2001.jpg)


![☆年長になっても、甘えさせえていいのかな?[6/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1044_img_01-200x3001.jpg)

![☆これって、「甘えさせ」?「甘やかし」? 後編[6/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1046_img_01-300x2001.jpg)


![嫌いになると、相手の話を聞けないガンコ脳になる [5/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_57.jpg)

![子どもの脳は、『○○しなさい』口調が大嫌い!? [5/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1034_img_01.jpg)

![家庭訪問、ママたちの素朴な疑問[5/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1043_img_01-300x2401.jpg)

![小さな子に、たくさん勉強させていいものなの? [5/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1033_img_01.jpg)
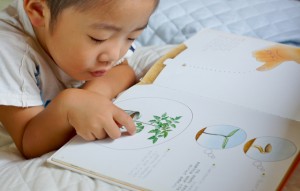

![★きれいに仕上がる上履きの洗い方は? [5/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1036_img_01-650x510.jpg)




![デコ弁『男の子おにぎり』の作り方 [5/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1024_img_01-520x510.jpg)






![家庭で「生活科」を教えることってできる? そのポイントは? [5/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_56-650x510.jpg)


![国語、算数、生活科!? 生活科ってどんな教科か知ってる? [5/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1031_img_01-650x510.jpg)

![★帰って来てからの習慣を身につけさせるには?[5/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/2051_img_01-480x510.jpg)

![気になる子どもの腹痛、受診のタイミングは? [5/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1030_img_01.jpg)
![☆「カゼでおなかが痛くなりやすい」のはもしかして… [5/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1029_img_01.jpg)


![★子どもの話をタップリ聞いてあげましょう [5/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1771_img_01-520x510.jpg)

![日焼け止め、帽子、衣服はどんなものを選べばいい? [5/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1028_img_01-520x510.jpg)


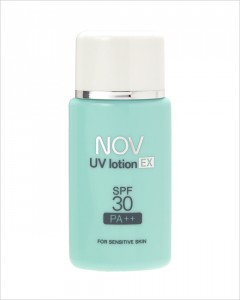


![★先生との間に溝があるようで不安なのですが? [5/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/2049_img_01-300x2401.jpg)

![年長になって1か月、子どもの気持ちは…? [5/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/05/3888_img_01-650x510.jpg)

![強い日差しから子どもの体を守ろう! [5/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1027_img_01-650x510.jpg)

![学校で子ども同士のトラブルが起こったらどうする? [5/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/2047_img_01-650x510.jpg)

![学校の宿題をやるのを嫌がるので困っています [5/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1021_img_01-650x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」 第5回 [5/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/090205.php_.jpg)
![朝、子どもが幼稚園に行きたくないと泣きます [5/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1020_img_01-650x510.jpg)

![デコ弁『女の子おにぎり』の作り方 [5/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1023_img_01-520x510.jpg)








![★子どもがマイペースなので、小学校生活が心配! [5/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1019_img_01-650x510.jpg)



