●とてもよくある小学生の物語
「むかし、むかし、あるところに」……
ではなく、「今の、今の、現代に」とある男の子がおりまして、その子は宿題への取りかかりが遅い子です。
宿題を目の前にしながら、一時間でも二時間でも平気でグズグズしています。
それで、お母さんは毎日イライラしています。
ある夜のこと、お母さんは「宿題やっておきなさいよ」と言い残して、近所の会合に出かけました。
約二時間後に帰ってきたときも、お母さんが家を出たときとまったく同じ状態で、その子は一問もやらないままグズグズしていました。
二時間もの間まったく無為に過ごしてしまったわが子を見て、お母さんは絶望的な気持ちになりました。
でも、会合の疲れもあってか怒る気力もなかったそうです。お母さんの頭の中はもう真っ白で、考える力もありません。
●お母さんのちょっとしたアイデアが子どもを救った
ところが、次の瞬間、お母さんの中にあるアイデアが浮かびました。
そして、紙に簡単な問題を書いたのです。3+2 8+4 5×3 などの単純な計算問題を五問です。
そして、「こういうの、できるかな?」と言ってみました。
すると、男の子は「簡単じゃん」と言ってうれしそうにやり始め、あっという間にやり終わりました。
おかあさんは、「すごいねえ!」とほめながら花丸を5つつけて100点と書きました。
そして、「ついでに宿題もやっちゃおう」と言ってみました。すると、男の子はそれまでグズグズしていたのがウソのように猛然とやり始め、あっという間に宿題をやり終わりました。
お母さんはびっくりしましたが、また大いにほめてあげました。そして、「これはいい」と直感しました。
それからというもの、お母さんは毎日ウォーミングアップ用に簡単な計算問題を作ってあげているそうです。
めでたし、めでたし。
●ちょっとした達成感でやる気スイッチを入れる
実は、この方法は脳科学的にも理にかなっているようです。
たとえ簡単な計算問題でも、やり終えて100点をもらい、ほめられるとうれしいものです。
それによって、ちょっとした達成感を味わえます。
すると脳の中の線条体という部位が活性化するそうです。そして、この線条体という部位が人間のやる気とか意欲といったものに大きく関わっているそうです。
ということで、なかなか取りかかれない子に対して、ガミガミ叱ってばかりいるのではなく、その子に応じたウォーミングアップを用意してあげるといいと思います。
やる気スイッチが入って、いわゆるエンジンがかかった状態にしてあげることが大切です。



![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第28回 [12/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_15.jpg)
![☆[入学準備]身につけたいこと必要度別チェック・家庭生活編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1166_img_01-414x510.jpg)






![☆[入学準備]身につけたいこと必要度別チェック・学校生活編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1165_img_01.jpg)




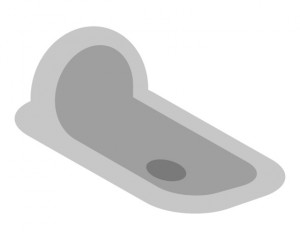
![☆[入学準備]身につけたいこと必要度別チェック・コミュニケーション&学習編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1167_img_01-585x510.jpg)








![☆入学準備にも役立つ!『こども手帳』の作り方[11/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/tecyo07.php_-461x510.jpg)


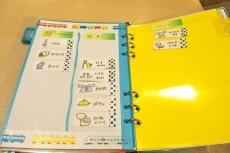


![デコ弁『ハムで電車』の作り方[11/21]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1161_img_01.jpg)









![手帳を作って、自分のことを自分でできる子に[11/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1163_img_01.jpg)

![★子どもに怒鳴ってしまうことがよくあります[11/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1158_img_01-409x510.jpg)



![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第27回 [11/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_14.jpg)
![イライラすると子どもをたたいてしまいます……[11/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1159_img_01-636x510.jpg)

![イライラしていた子も絵を描くことで心が落ち着く[11/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1153_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第26回 [11/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_13.jpg)
![なぜ歯並びが悪くなるの?[11/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1149_img_01.jpg)

![☆子どもの描いた絵からわかるSOSのサイン[11/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1152_img_01.jpg)

![デコ弁『魚肉ソーセージでおひめさま』の作り方[11/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1150_img_01.jpg)







![乳歯が抜けない、永久歯が生えてこない……どうすればいい?[11/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1148_img_01.jpg)

![☆ママ友から無視された…どうすればいいの?[11/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1145_img_01-507x510.jpg)

![☆ボスママから嫌われている…どうすればいいの?[11/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1146_img_01-604x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第25回 [10/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_12.jpg)
![デコ弁『ゆで卵でパンダ』の作り方[10/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1139_img_01-650x510.jpg)






![子どもと一緒に作ろう! ハロウィーンの飾り・小物[10/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1136_img_01.jpg)







![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第24回 [10/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_11.jpg)


![☆子どものうちから教えたいお風呂のマナー[10/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1135_img_01.jpg)

![いつからひとりで入れるの?[10/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1134_img_01.jpg)

![★へこたれない強い心をつくる男の子の育て方[10/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1133_img_01.jpg)

![★ママと男の子は、ラブラブな関係でもいいの!?[10/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1131_img_01.jpg)

![★「甘やかしすぎ」は、男の子の自立をジャマする[10/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1132_img_01.jpg)
