ゆで卵などの卵料理は、お弁当に欠かせないおかずですよね。ゆで卵をベース(土台)にすれば、動物のかわいいデコ弁パーツができちゃいます。
今回は、人気料理ブログ『*Ayano式* おとなごはん&こどもごはん』のフードコーディネーターAyanoさんに、まるまるとした見た目が愛らしい『ゆで卵でにわとり』の作り方を教えていただきます!
ゆで卵でにわとり
【材料】(1個分)
ゆで卵…1個
スイートコーン…1粒
ゆでにんじんの輪切り(2mm厚さ)…少量
※電子レンジで加熱して火を通してもOK。
焼きのり…少量
サラダスパゲッティ…少量
ハートのピック(赤色)…1本
【作り方】
1.ゆで卵でにわとりの土台を作る
ゆで卵を縦半分に切る。
2.のりで目・足爪を作る
のりをパンチ(またはハサミ)で丸・足爪の形にカットし、目・足を作って(1)にのせる。
3.とさか・くちばし・ほっぺを作る
ハートのピック(赤色)を用意する。スパゲッティは2mm長さに切り、スイートコーンに刺す。ゆでにんじんをストローで2枚抜く。
4.とさか・くちばし・ほっぺを固定する
ハートピックは(2)の頭の先の部分に刺す。
コーンはくちばしの部分に刺し、2mm長さに切ったスパゲッティでにんじんをほっぺの部分に刺したら完成。
※パーツ固定用のスパゲッティは、お弁当を食べる昼までには水分を吸ってやわらかくなります)。



![デコ弁『ゆで卵でにわとり』の作り方[10/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1128_img_01-650x510.jpg)






![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第23回 [10/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_10.jpg)
![☆子どものおやつは何を選べばいいの?[10/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1126_img_01.jpg)


![☆おやつのとり方で気をつけたいことは?[10/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1127_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第22回 [9/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_9.jpg)
![チックで、友だちにいじめられないか心配[9/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/09/1109_img_01-627x510.jpg)

![デコ弁『ウインナーでワンちゃんおにぎり』の作り方[9/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1120_img_02.jpg)









![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第21回[9/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_8.jpg)




![★3年生までは、外遊び中心の生活を[9/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1115_img_01.jpg)

![★どんな場所でも「外遊び」は楽しめる[9/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1116_img_01.jpg)

![脚が速くなるコツをマスターしよう![9/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1113_img_01.jpg)




![走り方を子どもに教えるときのポイントは?[9/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1114_img_01.jpg)


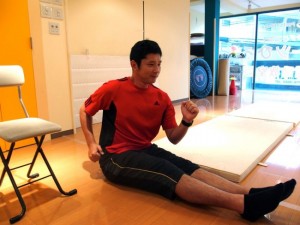
![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第20回[9/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_31.jpg)
![「速く走れる靴」って本当に効果があるの?[9/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1112_img_01.jpg)

![爪かみ、髪の毛抜き……、これってやめさせたほうがいい?[9/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1108_img_01-525x510.jpg)

![デコ弁当 『ウインナーでライオンおにぎり』の作り方 [9/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1107_img_01.jpg)








![☆「朝食はパン派」の家庭に知ってほしい注意点[8/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1104_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第19回[9/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_30.jpg)
![子どもの寝つきが悪い……どうすればいいの?[8/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1102_img_01.jpg)

![☆栄養バランスのとれた朝食で脳力アップ![8/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1103_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第18回[8/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_29.jpg)
![年長になったら「お昼寝」は必要ないの?[8/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1101_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第17回[8/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_28.jpg)
![学校でのウンチは、男の子にとって大問題[8/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1193_img_011-480x510.jpg)

![☆知っておきたい、トイレで失敗したときの対処法[8/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1092_img_01-640x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第16回[8/4]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_39.jpg)



