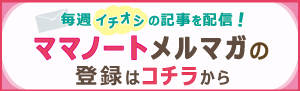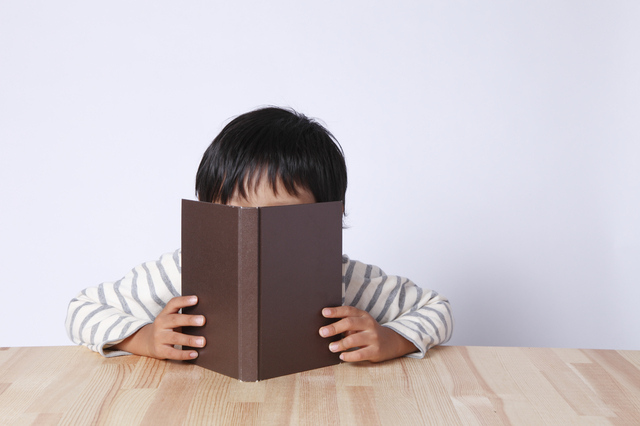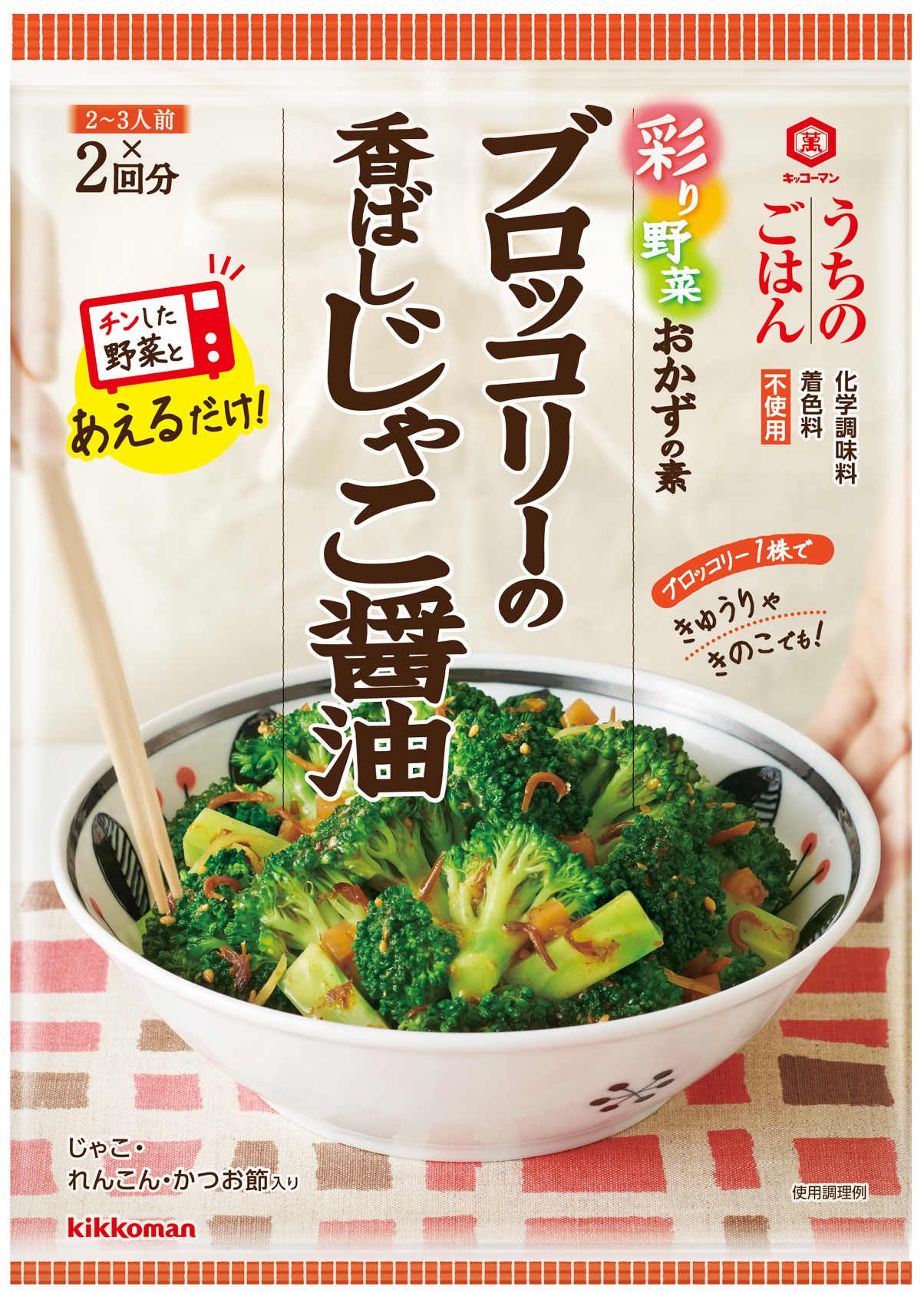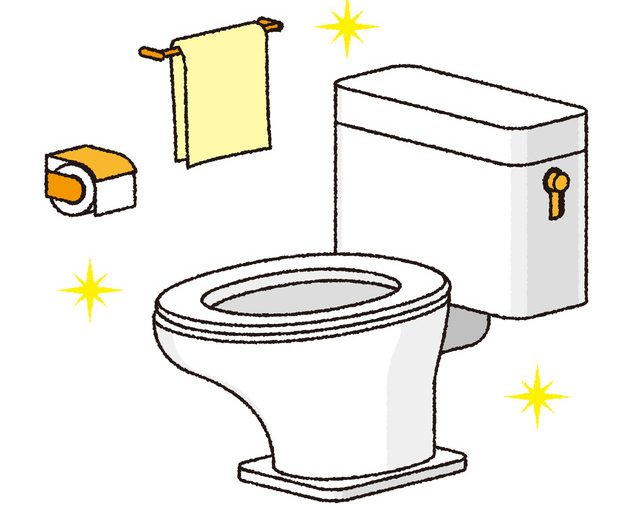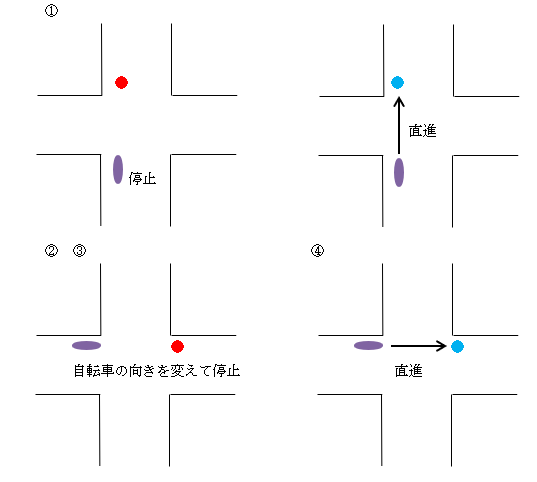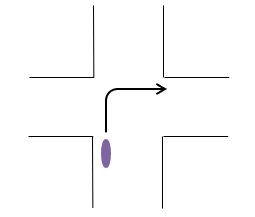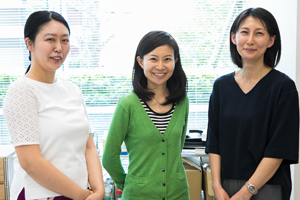家事に、仕事に、PTA活動に……毎日忙しいママたちにとって、食事の用意をする時間を作るのが大変なこともありますよね。でも、育ちざかりの子どもには、栄養たっぷりの食事を食べさせてあげたいところ。
そんなママたちに向けて、帰宅して10分で作れるような、簡単かつ栄養満点のメニューが掲載されているレシピ本を厳選しました!
●野菜をおいしく食べられるボリューム満点の一皿サラダ本
野菜が苦手なお子さんに手こずるママは多いもの。そんなときは、野菜以外の具をたっぷり加えた、一皿でメインのおかずになるサラダはいかがでしょうか?
『一皿でごちそう おそうざいサラダ』平岡淳子(ナツメ社)
この本に掲載されているサラダは、メインディッシュと呼べるほど、ボリューム満点! まずは定番サラダのレシピがあり、そこにさまざまな食材をプラスしてアレンジできるので、どれも簡単! 短時間で作ることができます。たとえば、シーザーサラダには、アボカドと生ハムを加えたアレンジや、まぐろとトマトを加えたアレンジが。卵サラダには、牛肉を加えたアレンジや、夏野菜を加えたカルボナーラ風のアレンジなど、少しの工夫で別のサラダに生まれ変わるレシピがいっぱいです。
また「肉・魚介類+野菜のボリュームサラダ」の章では、「ビーフステーキのサラダ」「しゃぶしゃぶサラダ」「お刺身サラダ」など、シンプルで簡単なサラダもあり、それぞれアレンジレシピが掲載されています。ほかにも、ご飯や麺をプラスしたサラダ、作りおきできるサラダなど、充実の180レシピを紹介しています。
●切り身やお刺身を活用した、お手軽な魚介料理が満載
子どもが食べにくいからと避けがちな魚料理。でも、たんぱく質やビタミン・ミネラルが豊富な魚は、育ちざかりのお子さんにぜひ食べていただきたい食材です。食べやすいものから慣らして、魚を食べるマナーも少しずつ覚えてもらうのはいかがでしょうか?
『魚屋三代目のうまい魚おかずBEST100』魚屋三代目(枻出版)
料理家「魚屋三代目」さんによるレシピ本には、簡単でおいしい魚のおかずがたくさん! 特に1章の「生で食べる」レシピ、2章の「焼く・炒める」レシピは、さっと作れるものが多いです。1章ではお刺身用の魚を使った「あじのグレープフルーツマリネ」や「いわしとトマトのカルパッチョ」、「甘えびのタルタル」など意外な洋風レシピも多数。あえるだけで作れるのも嬉しいところ。
2章では、さけ、ぶり、あじ、さば、いわし、かつお、かじきまぐろなどの切り身を使用。スーパーで買える、おなじみの切り身を使ったシンプルな照り焼きや、ソースをのせたオーブン焼き、簡単な揚げ焼きやソテーなど、時短レシピが満載です。
●お腹ペコペコさんには、2種類の食材だけで作る満腹レシピ本
小学生になると、学校での勉強や体育の時間、お友達と遊ぶ時間も増えて、お腹ペコペコで帰宅する子どもも多いもの。そんなとき、たった2種類の食材に味つけをするだけで、ボリューム満点の一皿が完成するレシピ本がこちらです。
『肉サラダ』堤人美(グラフィック社)
すべてのレシピが「肉(豚肉・鶏肉・牛肉)1種類」に「野菜1種類」のみを使用! たとえば、豚バラ肉といんげんを合わせたり、じゃがいもとグリルチキンを合わせたり、炒めた牛肉をトマトにのせたり……シンプルな調理法ながら味つけは凝っていて、2種類の食材でできているとは思えないほど豪華。買い物が楽なので、忙しいママには大助かり。
普段、頻繁に使わない調味料を含むレシピもありますが、塩やこしょう、みりん、料理酒、しょうゆ、酢など、家庭にある調味料でできるレシピもたくさん。簡単に作れるレシピ例に「焼きささみとズッキーニの南蛮風」「豚しゃぶのトロトロなす和え」「牛肉のバジル炒めとたっぷりトマト」などがあります。
●完全食品「卵」の魅力を解説しながら、アレンジレシピも多数紹介
血液や筋肉など、人の体を作る主成分となるたんぱく質は、子どもの成長に欠かせない栄養成分で、卵にも豊富に含まれています。また、卵が「完全食品」と呼ばれるのは、主要な栄養成分のうち、ビタミンCと食物繊維以外を含んでいるから。脂質やビタミン、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも豊富です。
でも、卵料理はワンパターンになりがち。そこで、卵に関するさまざまな疑問や不安に対する答えとともに、おいしい卵レシピを紹介してくれるのがこの本です。
『卵は最高のアンチエイジングフード』オーガスト・ハーゲスハイマー(三空出版)
卵の栄養成分の解説をはじめ、「コレステロール値が高い」という噂の真偽、さらに2人の医学博士のインタビューも掲載され、読みごたえがあります。読むと「子どもの成長のために、卵をもっと取り入れたい」と感じるはずです。
レシピページには、パルミジャーノとローズマリーを加えた風味豊かなスクランブルエッグや、焼いたトマトと茄子と目玉焼きを重ねたもの、葉野菜と卵を入れたチキンスープなど、簡単でアイデアフルな卵料理がいっぱい。卵は朝に食べるイメージが強いですが、夜ご飯のメニューにもなるものが見つかりますよ!
●簡単に栄養をプラスできる、具だくさんおむすびのレシピ本
何種類もおかずを作る時間がないときや、時間がなくて慌てて料理をするときは、具だくさんのおむすびや混ぜごはんが便利!
『恋するおむすび』SHIORI(枻出版)
この本は、さまざまな食材で作る「おむすび」レシピの一冊ですが、混ぜごはんのアイデアにも使えます。ひじきとそぼろを加えたり、ホタテの水煮とかぶの葉を加えたり、牛肉とごぼうを煮たものを加えたり、ネギ塩と豚肉をゆかりごはんに入れたり……さっとごはんに混ぜるだけで、栄養豊富な混ぜごはんが完成します。
また、基本の鮭・梅・たらこのおむすびのバリエーションも掲載。鮭と枝豆、梅と野沢菜、梅としらす、明太子とクリームチーズなど、さまざまな組み合わせが紹介されています。少し時間はかかりますが、ローストビーフ巻きや豚肉巻き、から揚げや海老マヨ入りなど、ボリュームのあるおむすびも紹介されています。
さらに、お米の種類やおいしい炊き方、保存術などのコラムも充実しているので、お米が好きなお家のママはぜひ参考にしてみてください。
今回は、時短でも作れる栄養たっぷりのメニューが満載の本を紹介しました。どんなに忙しくても、わが子に栄養あるごはんを食べさせたいと思うのが親心。少ない手間で、短時間でできるレシピを探して、育ち盛りのお子さんたちのお腹を満たしてあげてくださいね。
(選書・執筆:富永明子)
関連記事はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓