●進学、進級して1か月の子どもたちのこと
こんにちは、たっきーママです。
早いものでもう5月!
我が家の子ども達も進学、進級して1か月。長男は中学校に入学しました。
長男の通う中学校は3つの小学校から集まったので、新しいお友達もたくさん。
人見知りでおとなしめの長男を心配していましたが、どうやら新しい友達も出来てなかなか楽しいようです。
子どもって順応性あるなぁ。
GWで振り出しに戻ってしまわないことを祈る(笑)
今回は「貝」がテーマですので、あさりを使ったレシピを。
潮干狩りに行かれる方も多いかと思いますので
たくさんあさりがとれたら是非!
あさりとキャベツのみそクリーム煮
【材料】(2人分)
キャベツ…1/8個
玉ねぎ…1/4個
バター…10g
粗挽き黒こしょう…適量
あさり…200g
水…100ml
酒…大さじ3
★牛乳…200ml
★みそ…大さじ2
【作り方】
1. キャベツはざく切りにし、玉ねぎはくし形に切る。あさりは砂抜きをしておく。
2. フライパンにバターを熱して溶けたらキャベツと玉ねぎを加えて炒める。しんなりしてきたら、あさり、水、酒を加えてふたをし、5分蒸す。
3. あさりの口が開いたら、ふたを取って★を加える。みそを溶かしながらひと煮立ちさせ、粗挽き黒こしょうをふる。
粗挽き黒こしょうはお好みで。塩、こしょうをふってもOKです。
個別にお皿に取ってから、大人だけ振っても!
前回の記事はこちら
たっきーママさんの他記事はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓



![☆貝おかず「あさりとキャベツのみそクリーム煮」[2016/5/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/c229a6d84b5b023aec536d9f8309289c-825x510.jpg)


![☆きのかんちの「まいぺーす入学準備マンガ」第2回[2016/5/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/5b50fd1577f3fb7ea7693e8443991e22.jpg)


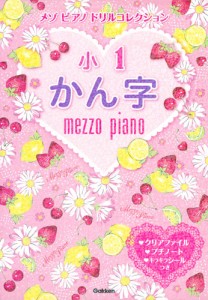
![☆運動会、悔しい結果に落ち込む子をなだめたいときは?[2016/5/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/pixta_2497792_S.jpg)

![★言われなくても宿題をする子になる6つの方法[2016/5/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/de7fb14e96f575e20c7ed4007fccd43d.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第3回[2016/5/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/04/pixta_2194006_S.jpg)

![☆運動会の練習で、弱音をはく子を励ますには?[2016/5/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/09/pixta_470275_S.jpg)

![★突然の集金あり!?「小学校でかかるお金」準備のコツ[2016/4/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/0ed01b8f8e7e75cefd975fee3033a11b.jpg)

![★PTAを「やる人」「やらない人」で、もめないためには? [2016/4/28]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/05/pixta_9795031_S.jpg)

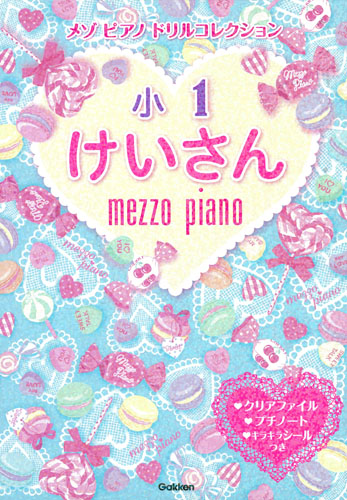
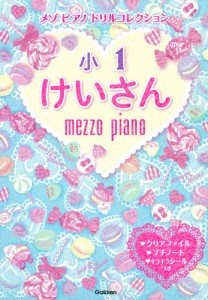
![★PTA委員・役員決めは、すんなりいかないもの? [2016/4/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/05/pixta_21045802_S.jpg)

![☆きのかんちの「まいぺーす入学準備マンガ」第1回[2016/4/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/05/071639e0e7fa34ed7cbcd831c2a1e7e0.jpg)

![★PTAになると、どんなメリットがあるの? [2016/4/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/04/pixta_16978117_S.jpg)

![☆新連載が始まります![2016/4/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/828acefc97465c4795c0bd4f14cbee1e.png)


![★「PTAは面倒そう」は思い込み? [2016/4/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2014/04/pixta_13180255_S.jpg)



![☆旬おかず「新じゃがとベーコンのはちみつ醤油煮」[2016/4/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/3d113c9614b0c01f7121e46d822f7b4b-825x510.jpg)

![☆年下の子を叩いてしまったわが子。どうすればいい?[2016/4/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/da9c9365b2a028ec0ad65890166e9556.jpg)

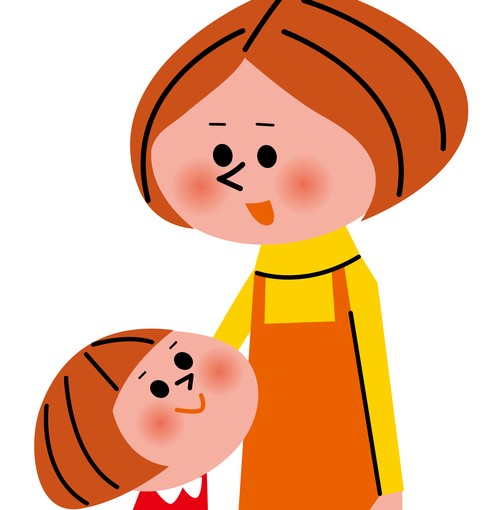

![★G.Wは、ゆったりスケジュールで楽しんで[2016/4/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/0420g.w1.jpg)

![★親野智可等の「ママも小学1年生」第2回[2016/4/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2013/04/pixta_13983982_S1.jpg)

![☆小学校の先生と信頼関係を築く方法は?[2016/4/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/04/pixta_10420224_S.jpg)

![☆親に頼らず「自分でできる子」になる家庭ルール[2016/4/14]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/04/pixta_12205993_S-496x510.jpg)

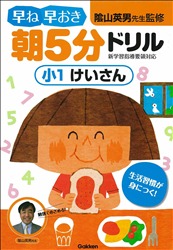
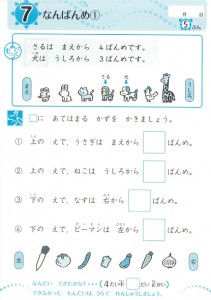


![☆入学後の友達関係、登下校の不安を解決![2016/4/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/04/pixta_14400315_S.jpg)

![☆文字や数の覚えが遅くて心配…先輩ママの解決法は?[2016/4/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/04/pixta_20991919_S.jpg)

![☆宿題、忘れ物…入学後の子にはどんな気配りが必要?[2016/4/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2012/04/pixta_20991898_S.jpg)

![★登下校中、子どもが不審者に会ったらどうする?[2016/4/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/3fb71510b4778ae4a8221398ca6ff057.jpg)



![☆旬おかず「春キャベツと桜海老のクリーミーサラダ」[2016/4/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/5ba4a1700a6eab7cdbc6bf7c4e772b5a-825x510.jpg)

![★登校班、ママたちは何が心配?[2016/4/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/04/7c85500e82b953addf73be63650a06fe-428x510.jpg)
