2日目(火曜日)
ミックスベジ入りハンバーグ弁当
献立
■主食:ごはん
■ごはんデザイン:パセリ ミックスベジ(炒めたもの)
■主菜(赤):ミックスベジ入りハンバーグ
■主菜(黄):かぼちゃ(冷凍のもの)じゃがいものチーズ焼き
■副菜(緑):カラーピーマンと小松菜のソテー
■隙間:ミニトマト
〈前日準備〉
・前日の夕食作りのついでにいも類以外の野菜を切り、冷蔵する。
・ミックスベジを混ぜこんだハンバーグだねを作り、成型してラップでつつみ、冷蔵する。
〈ポイント〉
・ハンバーグをフライパンで焼くとき、空いたスペースにカラーピーマンを入れて同時に炒めれば時短に。
・市販の冷凍カットかぼちゃ、じゃがいもスライスをそれぞれラップに包んで電子レンジで加熱。アルミカップに入れ、溶けるチーズをのせてトースターでチーズがとけるまで焼く。



![子どものお弁当・5日間献立(2日目)[8/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/403a0394ab2f1feed54b419237698615-825x510.jpg)

![学校とのやりとりがうまくいかないときは?[8/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/18ef86f00b4b7cc3a1f315410b31fe1c.jpg)

![先生とのやり取りのポイントは?[8/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/125b52bf6746df5db08d3f2a6dc395d1.jpg)

![☆子どもの兄弟姉妹ゲンカを減らす方法[8/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/b62646f0f652d380be700f81b50b2b3f-640x510.jpg)


![困ったことや要望を、学校にどう伝える?[8/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/6c016a6827db652bdcf1d24e000c97c1.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第13回 [8/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_14693028_S-640x510.jpg)

![火を使わない!「レンジでカレーチャーハン」[8/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/e30e8aa84f0e40d53b840d958c5280db-825x510.jpg)

![給食を作る場所はどこ?[7/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/07_01.jpg)


![冷やし中華風「しっとり蒸し鶏の彩りそうめん」[7/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/e6b85fe5839efa46bf1f53389cbe391e-825x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第12回 [7/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_14739423_S-640x510.jpg)

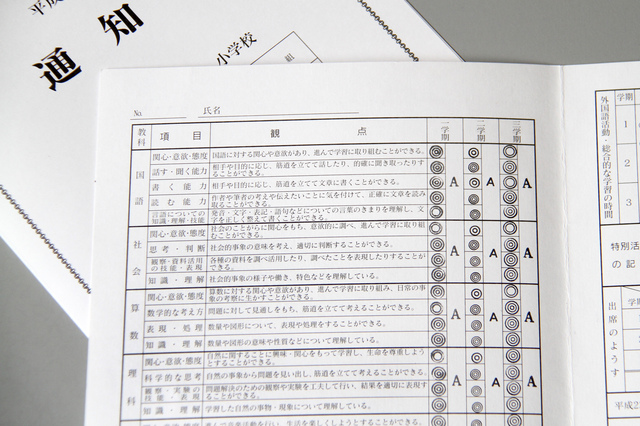
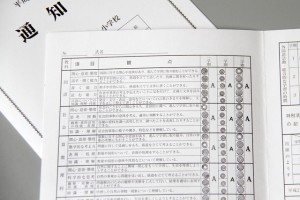
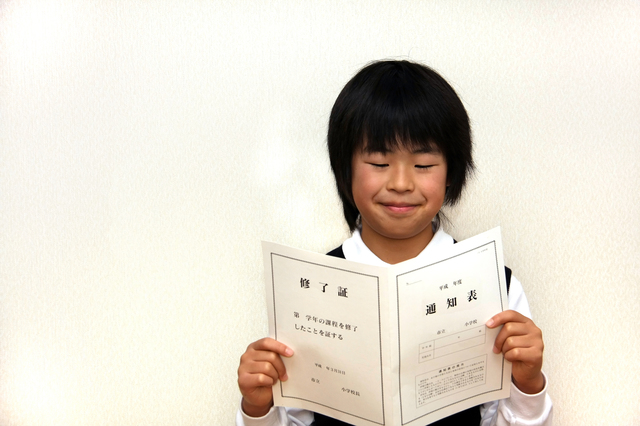
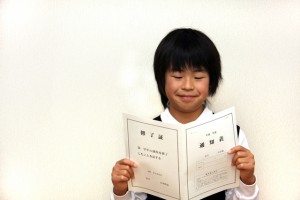
![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第11回 [6/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_4016512_S-640x510.jpg)

![☆失敗しても折れない心の子に育てる3つの方法[6/26]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/8d887b6a736b2a91ec47c9d72ff349f7.jpg)



![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第10回 [6/22]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_2104950_S.jpg)

![残り野菜でできる「ベーコンとキャベツのパスタ」[6/19]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/120ae50873751ee0cb9547a363a48d07-825x510.jpg)

![新しい制度のスタートで、学童保育が変わる!?[6/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/shien1.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第9回 [6/15]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_2435605_S.jpg)

![学童保育の指導員が資格化されました[6/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/shien2-640x510.jpg)

![学校給食の現場をのぞいてみよう[6/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/3e70f33a4fbae2314b860134799087bd.jpg)




![小学校受験に合格する子の共通点とは?(その2)[6/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/a1f818356525edf154383111ba47a058.jpg)

![小学校受験で面接官が見ているポイントとは?[6/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/ac18738bcd2fdd056be6a0bf42f88f26.jpg)

![小学校受験に合格する子の共通点とは?(その1)[6/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/b328cac0f0ae10379840d2e4540ff3ad.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第8回[6/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_14100229_S-640x510.jpg)

![梅雨どきにオススメ「豚こまの簡単梅マヨ炒め」[6/5]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/c229a6d84b5b023aec536d9f8309289c-825x510.jpg)

![「上の子」の困った行動をやめさせる方法は何?[6/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/962ac4d225a06dab3a1eb2ba336f0b34.jpg)

![「上の子」がわがままを言うのはなぜなの?[6/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/f07d1c17ffcf67fb39d579dee9f72916.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第7回[6/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_8179162_S-640x510.jpg)

![フードつきの服は危なくないの?[5/29]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/bf6981f9d4a52afa9cce5bb4dc2cc842.jpg)


