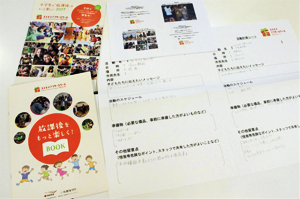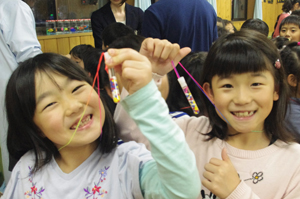スマホの普及で子育て情報が増えた
今の社会は情報が溢れています。
特にスマホが普及してからは、その量が爆発的に増えました。
でも、情報というものは、増えれば増えるほど玉石混淆な状態になるものです。
つまらない情報ばかり読んでいる人と、意味のある有益な情報を積極的に取りにいく人とでは、大きな差が開きます。
子育て情報もスマホの中にどんどん入ってきます。
有益な情報を読んで我が身を振り返ったり、新たなことを試してみたりするのはとてもよいことであり、子どものためにもなります。
情報がかえって子育てを大変にしてしまう
でも、それらの情報がかえって子育て中のママ・パパを大変にしてしまう側面もあります。
例えば、「叱ってばかりだと弊害があります」と書いてあるのを読めば、誰でも「なるほど。気をつけよう」と思います。
でも、決意したからと言って簡単に変われないことも多いわけで、しばらくすると同じことを繰り返してしまうということもよくあるはずです。
そこで、「私はなんてダメな親なんだ」と落ち込んでしまい、それがまたストレスになってしまうということもあるでしょう。
そして、そのストレスがまた子どもに向かってしまうということもあり得ます。
自分を責めてしまう人は、開き直ることも必要
真面目すぎて、すぐ自分を責めてしまう人にはありがちなことです。
これは、その人自身の生まれつきの資質にもよることもありますし、親から受けたしつけによることもあります。
つい自分を責めてしまう人は、一度開き直ることも必要だと思います。
例えば、相田みつをさんを真似して、「つまづいたっていいじゃないか にんげんだもの」と言ってみましょう。
もっと短く、「にんげんだもの」とつぶやいてみるのもいいですね。
同じく相田みつをさんの「おたがいになぁ 不完全 欠点だらけの にんげんですがね 」という言葉も素敵です。
親子ともどもお互いにしょうもない人間同士ということで、自分を許して子どもも許してあげてください。
自分をほめてあげよう
自分で自分をほめてあげることも大切です。
「自分もけっこうがんばっている」とほめてあげてください。
「そもそも生んであげただけでもすごいことだ」と思ってみるのもいいでしょう。
仕事ではほめられても、子育てというのはあまりほめてもらえないものです。
子育てはしっかりやって当たり前と思われてしまいがちなのです。
旦那も奥さんもほめてくれません。
おばあちゃんおじいちゃんもほめてくれません。
先生もほめてくれません。
子どももほめてくれません。
だ~れもほめてくれません。
ですから、自分で自分をほめてあげてください。
最後にまとめです。
有益な情報を積極的に取りにいき、実践することは大事です。
でも、できないからと言って自分を責めないでください。
自分を許して子どもも許し、自分で自分をほめましょう。
親野先生の連載はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓



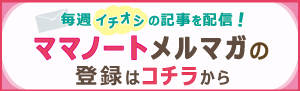
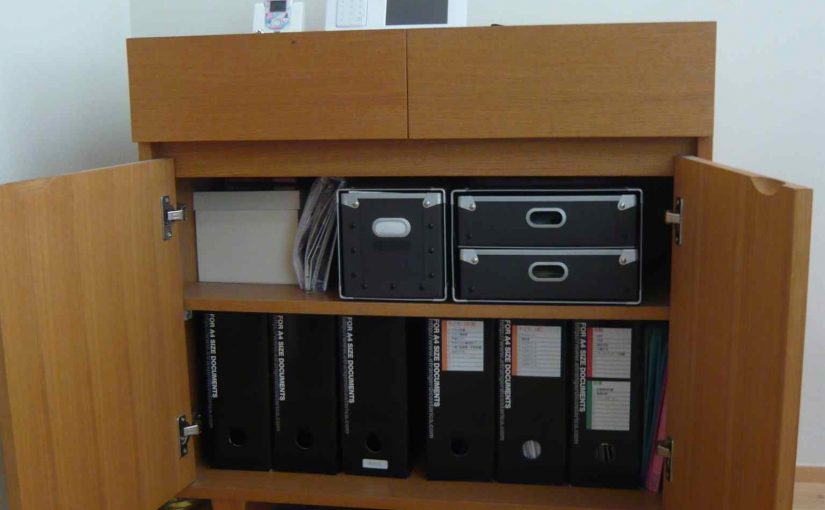

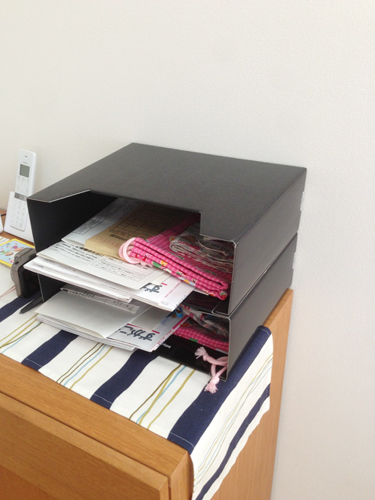
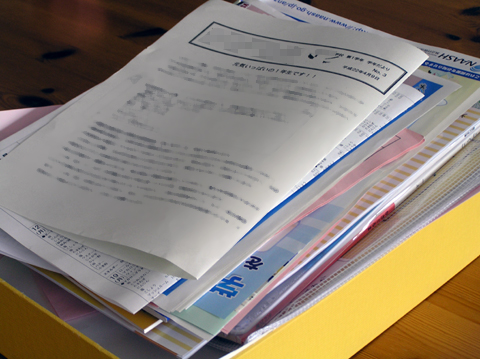
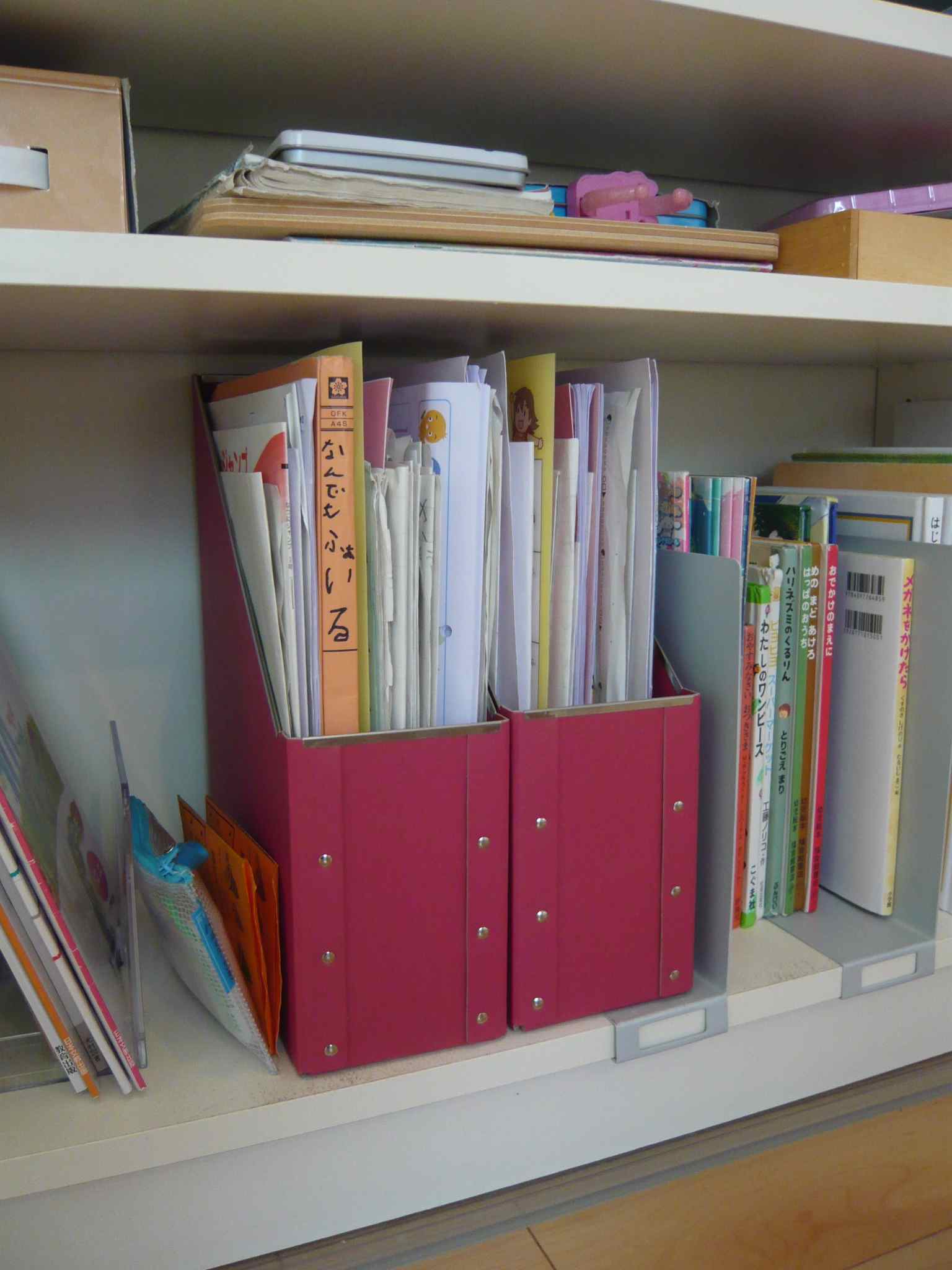
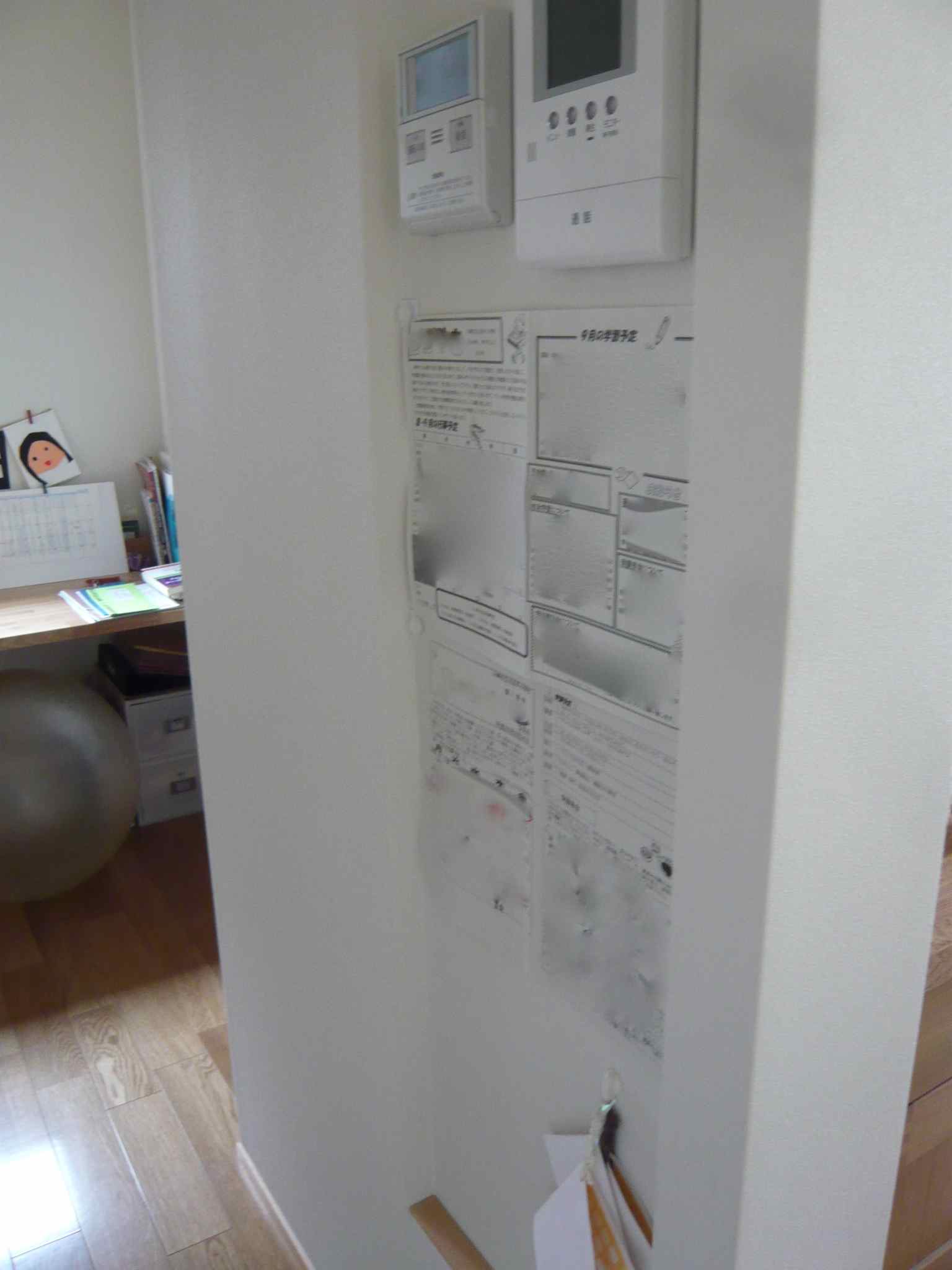


















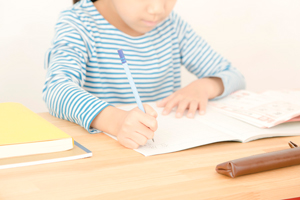
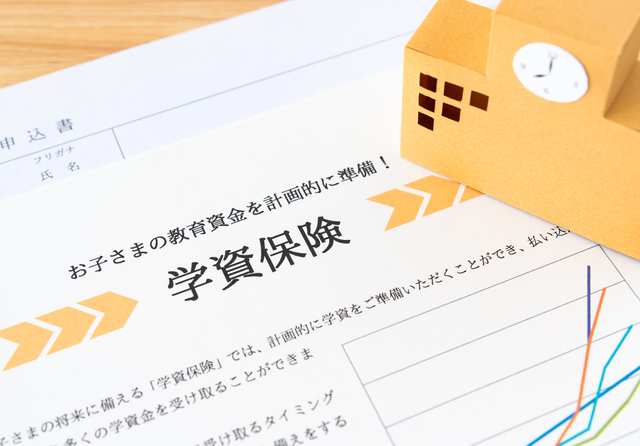









![先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.4]後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/11/53f4e04a162e2957bda01de614d7d9d3.jpg)