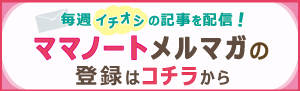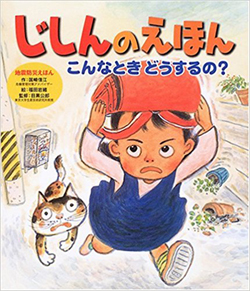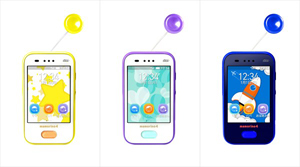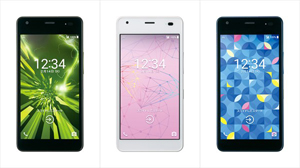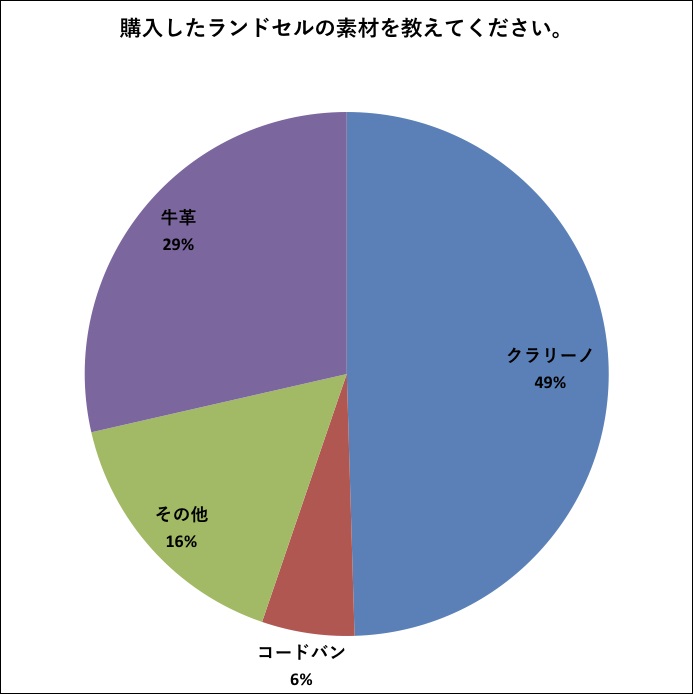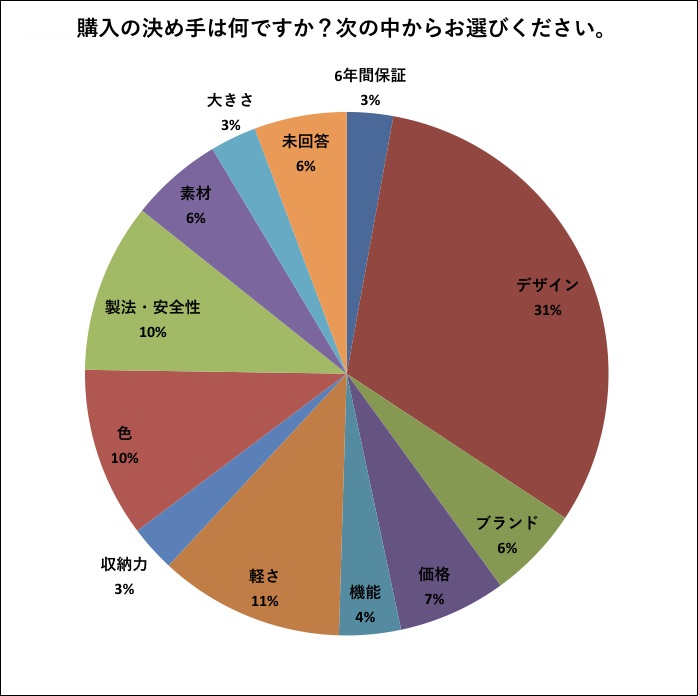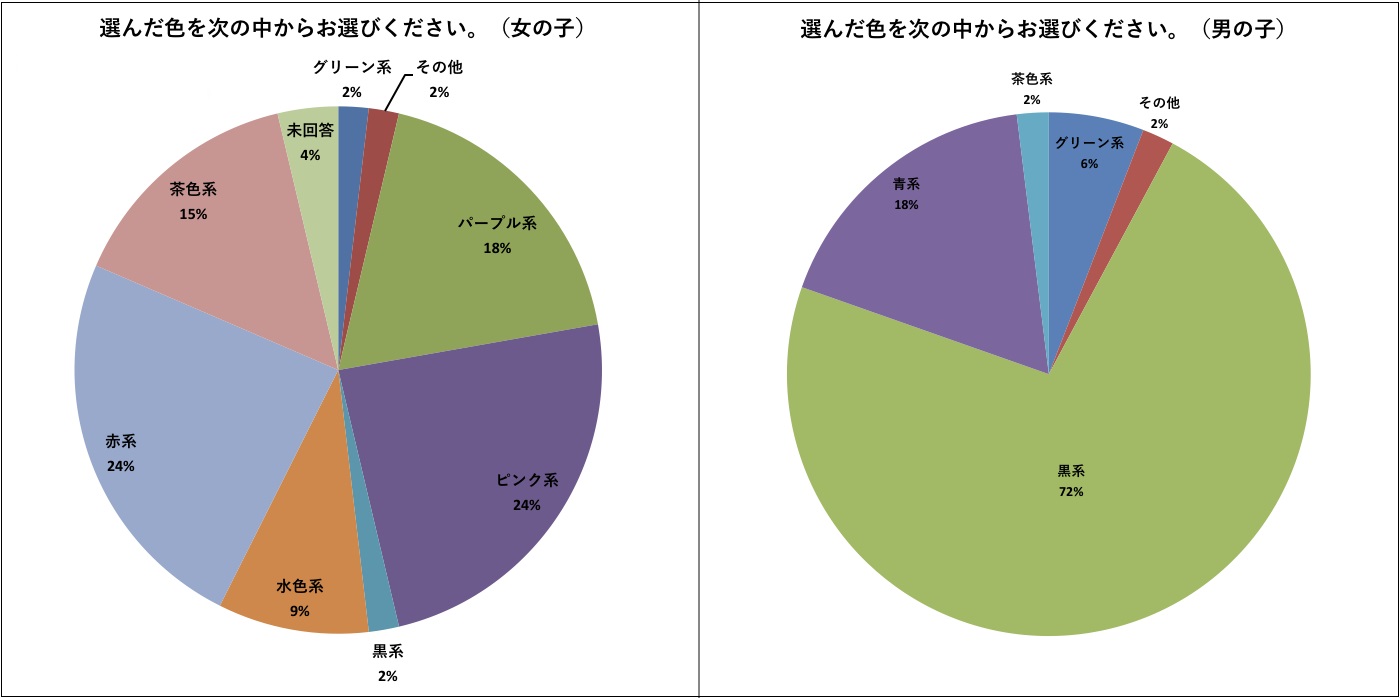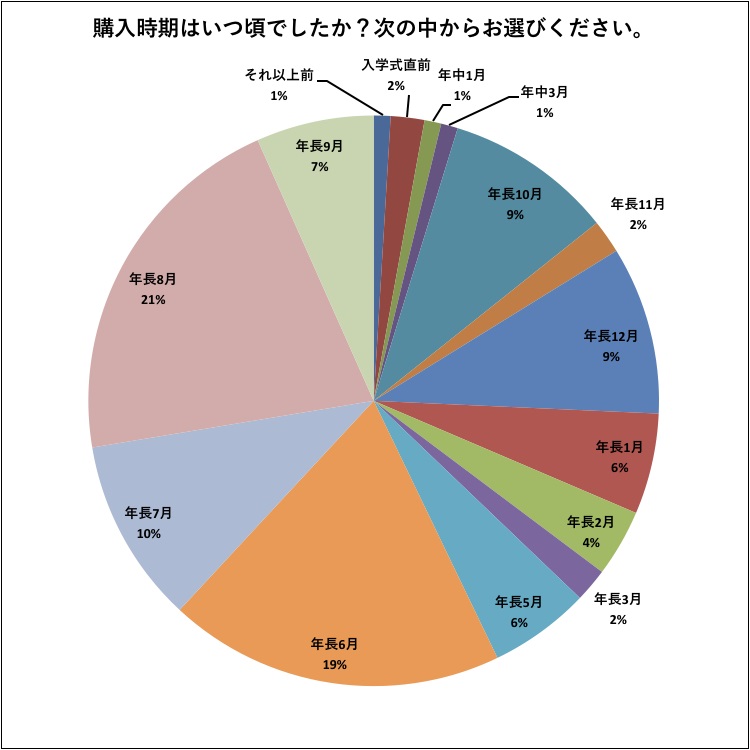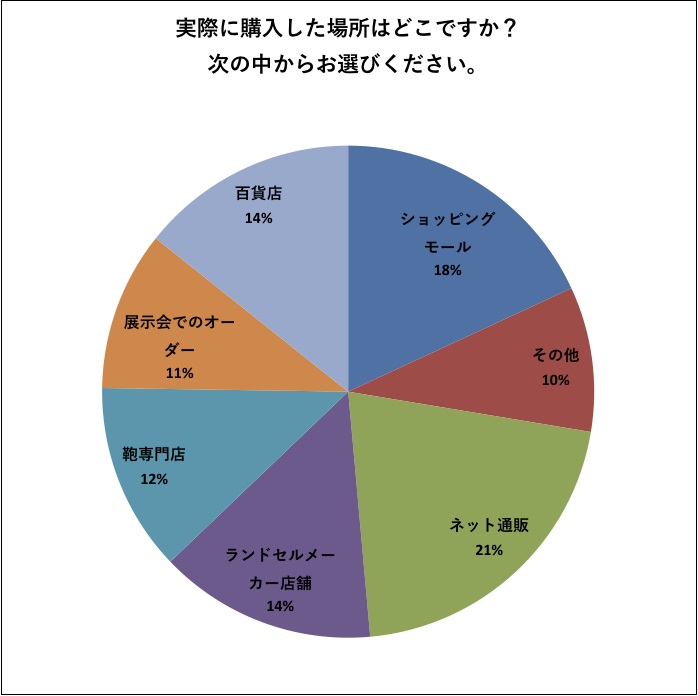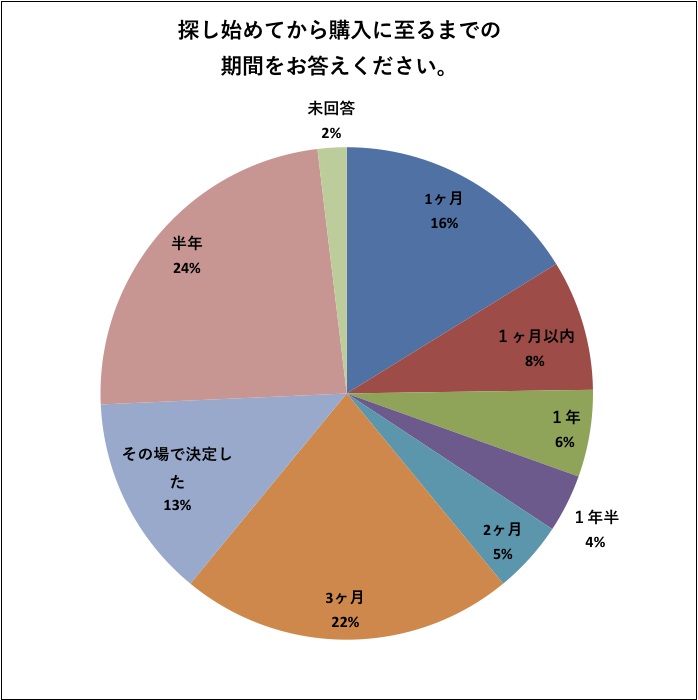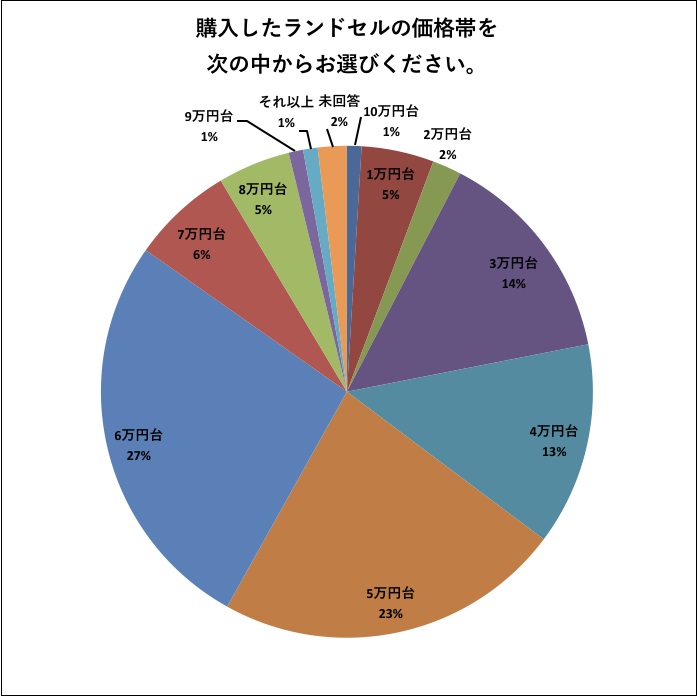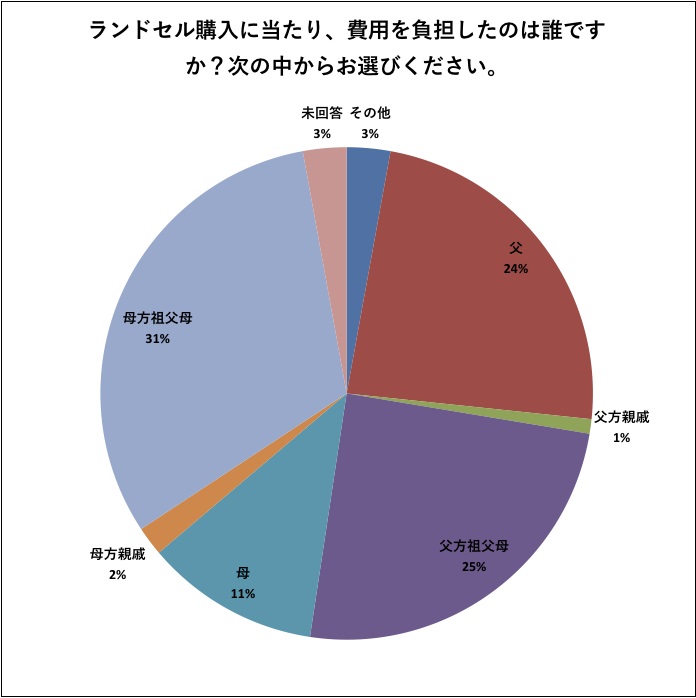こんにちは、現役小学校教諭の舟山由美子です。
この連載も最終回です。最後に、これからどんどん成長していくわが子をどう見守っていくか、教師の立場からお話しさせていただきたいと思います。
●子どもの様子やしぐさから感じ取って応える
これはママノートの読者の方には、少し先の話と感じるかもしれませんが、思春期以降の子どもの問題行動に悩んでいる保護者の方に対して、ある医師がこんなふうに言っておられました。
「子どもを甘やかしてください。甘やかすといっても、子どもの言いなりになるとか、子どものご機嫌をとるとか、何かを買ってやることではありません。今、子どもが何を思っているのかを察して、親が行動するのです」
例えば、学校で行事があって疲れて帰ってきたら、「お帰り。ジュースでも飲もうか」と言って、子どもがひと息ついたら、ぽつぽつ話を聞く…など、大人でも自分がそうしてほしいなと思うことを小さい頃からしてやる。この積み重ねが大事なのだそうです。
つまり、親の「感受性」だけでなく、「感応性」が大事だということなのでしょう。「感受性」だけだと、受けとめるだけになりますが、「感応性」は、子どもの言葉からだけでなく、様子・気配・しぐさなどから感じ取って応えようという具体的な行動であり、さらに一歩進んだ大人の感性が問われます。
赤ちゃんのときは、眠っていても息をしているかどうか不安でよく観察をしたのではないでしょうか。成長した今、自分でほとんどのことができ、言葉も話し、文字も読めるのですが、「ことば」を超えた「なにか」を感じて応じることをおろそかにしてしまうと、子どもの心が、親から離れてしまうこともあるでしょう。
●周囲の大人との連携も必要なこと
かといって、心配だからと、あれこれ口を出し、手を出していたら子どもは自立できません。親から何か言われないと、何もできない人間になるか、ある時期からはうっとうしがられて避けられてしまいます。こちらは「感応性」の気持ちで子どもに近づいても、ぷりぷりして、何も答えないかもしれません。
言いたくないことがあるときは、無理に聞き出したりせず、「どうしても困ったときは、必ず言ってね」とだけ言いましょう。あとは、その子が一人で乗り越えるかもしれないし、やはり悩んでしまうかもしれません。でもこれは、大人がみんな通ってきた道。お風呂に入ったときにでも、「昔、お母さん、こんなことあってね…」などと話すだけで、解決することもあるし、ずっとあとになって、子どもが打ち明けてくるかもしれません。
学校でのこと、友だちとのことなど、子どもなりにいろいろな経験をして大きくなります。親御さんは先回りして心配してしまいがちですが、子どももプライドがあります。
ただ、昨今のいじめ問題の報道を見ると、やはり心配になるのは当然かもしれません。教師として力を尽くしていても、これはとても難しい問題だと感じます。だからこそ、大人は大人としての対応と、大人同士(教員・保護者・地域の方)の連携という知恵と努力が必要なのだと思うのです。いろいろな人の目で見守ってもらって、育ててもらい、自分たちもみんなで育てていく、という姿勢が大事だと思っています。
●親しかできないことがあるときは、すぐに行動を
よく親御さんは我が子に「思いやりのある子に育ってほしい」とおっしゃいます。
そのために必要なのは、
・子どもが思いやりのある行動をされたことがある
・思いやりのある行動を常に身近で見て育っている
・思いやりのある行動をして、褒められた経験がある
ということだと言われます。
つまり、どういう子どもに育ってほしいかということは、保護者の方が、ふだんどんな行動を子どもにしているか、ということになります。
もちろん、大人は大人の生活があり苦労があります。いつもいつも、子ども最優先では生活できません。けれども「あっ、今、この瞬間に、親しかできないことがある」と思ったら、すぐ行動するべきです。思春期以降のために「貯金」しているという気持ちで、疲れた体にむち打ってでも関わることも必要かもしれません。
そして意外と大事なのは、学校行事に親御さんができるだけ参加すること。これがよい結果を生むことが多いように感じます。子どもは(特に高学年になると)親が学校に来るのを嫌がる傾向があります。それでも、自分に関心を持ってくれていることは理解しています。
親にとっては集団生活の中のわが子の姿、というのを冷静に見る機会でもあり、子どもからすれば、「親は、忙しくても、いつも学校に来てくれた」といつか思い出し、それが次の世代にもつながり、子どもを大事にするという感覚が継承されていくのだと思います。
『学童期の子育ては、親の黄金期』です。苦しいこともありますが、振り返れば楽しいことばかりが思い出されることでしょう。どうか、この時期を大切になさっていただきたいと思います。
舟山由美子先生の連載はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓