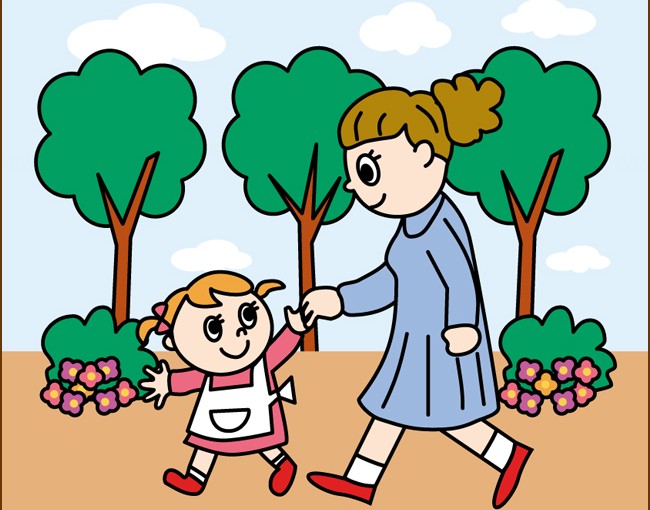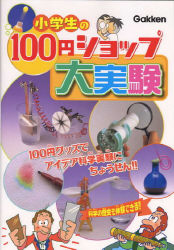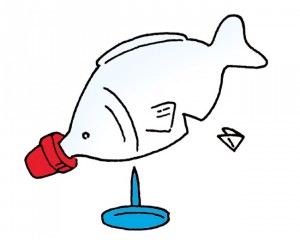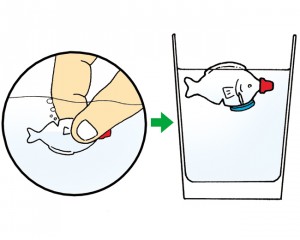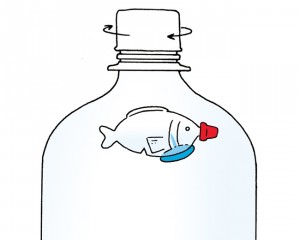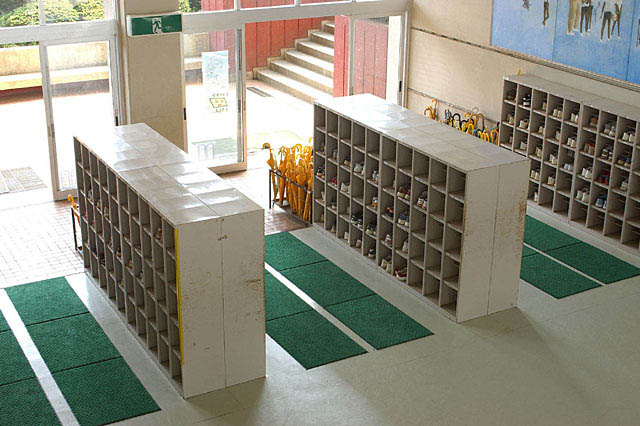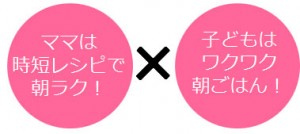前回では、キャンプを始めたい初心者の方へ、何から始めるべきかをレクチャーしてもらいました。
キャンプに慣れてきたら、そろそろ自分たちの道具が欲しくなるものです。
今回は、まず揃えたい道具の選び方のポイントや、おすすめ商品、注意点などを、引き続き、「週末キャンプ&アウトドア」の大迫さんにお聞きしました。
初心者が揃えたい道具と言えば、テント、タープ、寝袋、グラウンドシート、テーブル、イス、ランタン、バーナーなど……、というお話でしたが、その中でも、まず必要なものはなんでしょうか。
大迫 「テント、イス、テーブル、タープ、ランタン、それにバーナーですね。
順にポイントを挙げていきましょう。
●テント
・選び方のポイント
設置も簡単、軽量でコンパクトに収納できるドーム型がいいと思います。
種類も価格帯も豊富ですよ。
大きさは、家族の人数プラス1~2人分ほど余裕をみましょう。
なかでもおすすめなのは、
入口に前室やキャノピー(大きなひさし)が付いたもの。
この部分に荷物の収納ができるので、テントの中を広々と使えます。
雨の日なども出入りしやすく、簡易なタープ替わりにもなるものもあります。
・おすすめ商品
コールマン BCワイドドーム/325
・注意事項
テントだけでも使えますが、テントの床面を湿気や砂利の突起物など
から保護するシートや、
断熱やクッションのためのテントマットなどがあると、快適に休めます。
テント内では火気厳禁です。
一酸化炭素中毒や、火事などの危険性があります。
●イス、テーブル
・選び方のポイント
テーブルはキャンプサイトの中心であり、憩いの場です。
食事をしたり、料理をしたり、いろいろな作業を行いますから、
こだわって選んでみましょう。
1泊であれば、イスもセットされているコンパクトなタイプを。
設営や撤収が便利です。
グレードアップしたテーブルが欲しくなった時でも、
サブテーブルとして出番はありますよ。
次にイスですが、
のんびりしたい派はゆったりくつろげるイスを選びましょう。
機動性優先派は、快適性をある程度犠牲にしてでも
コンパクトに収納できるものを選ぶといいと思います。
テーブルとイスの出番はキャンプだけではありません。
ガーデンパーティやベランダパーティでも重宝します。
使い方にあわせたサイズや機能を考えて購入するといいですよ。
・おすすめ商品
コールマン ファミリーベンチセット/ミニ
●タープ
・選び方のポイント
日よけ、雨よけ、風よけを兼ねるのがタープです。
いろいろ種類はありますが、夏のキャンプを快適過ごしたいなら、
メッシュのテント状のスクリーンタープがおすすめです。
まわりがスクリーンになっているので、
暗くなると出てくる害虫や蛾から、テーブルまわりをガードできます。
四方が囲まれた感覚も、家族に安心感を与えてくれます。
・おすすめ商品
コールマン スクリーンキャノピータープⅡ
●ランタン
・選び方のポイント
夜のテーブル周りを照らす明るいランタンは
ガソリンやカセットガスなどの燃料式と電池式、どちらでもかまいません。
扱いは、電池式→ガス式→ガソリン式、の順に難しくなります。
それぞれに明かりの雰囲気も違いますので、好みで選んでみましょう。
夜遅くなると、キャンドルだけでも、雰囲気が出ていいですね。
・おすすめ商品
コールマン クアッドLEDランタン
・注意事項
テント内では、絶対に火を使ってはいけませんので、
テント内で使うランタンは、電池式にしましょう。
夜の水場やトイレなどに行くときや、テント周りの点検時も、電池式電灯の方が便利です。
電池式のヘッドランプや肩掛け式なら、両手が使えるので安全です。
●コンロ
・選び方のポイント
木炭などを使う焼き物用のバーベキューグリルから、
ガスやガソリンなどを使うコンロ(バーナー)まで、
各種ありますが、焚口が2個あるツーバーナーが基本です。
おすすめはガス式。
家庭のガスコンロのように、ひとひねりで着火するので便利で安全です。
ランタンやバーナーなどのボンベの規格を統一させるのも、賢い選び方です。
また、キャンプらしさを味わえる
バーベキューグリルはどうしても欲しいところですね。
週末のレジャーやホームパーティでも活躍するでしょう。
自立式のもの、テーブルの上で使えるもの、
コンパクトに収納されるものなど各種ありますので、
それぞれの使い方や料理する量にあわせて選びましょう。
バーベキューグリルは、
キャンプ場によってレンタル品があったり、
かまどの設備が用意されていることもあります。
キャンプ場選びのときに、チェックしておきましょう。
料理の道具は家庭用のものを持っていってもいいでしょう。
卓上ガスコンロも、家庭用調理鍋もキャンプ場で使えます。
ベテランになると、中華鍋やすき焼き鍋を駆使して料理する人や、
焼き鳥や焼き魚のために七輪を持ち込む人もいますよ。
・おすすめ商品
コールマン パワーハウスLPツーバーナーストーブⅡ 」
ポイントを押さえれば、
初心者でも楽しく道具選びができそうですね。
次回はキャンプの醍醐味、食事についてご紹介。
おすすめレシピや、キャンプクッキングでの簡単なアドバイスをお届けします。