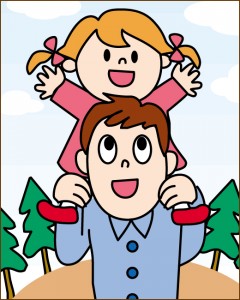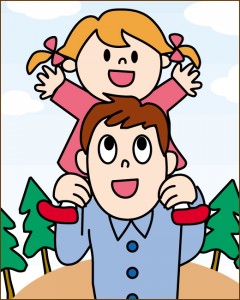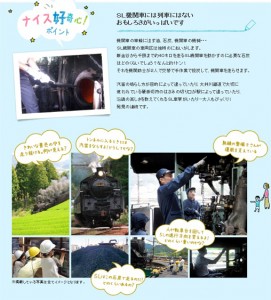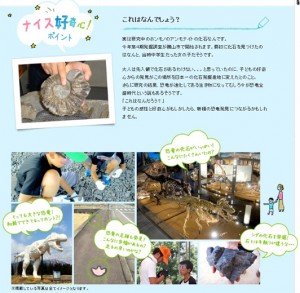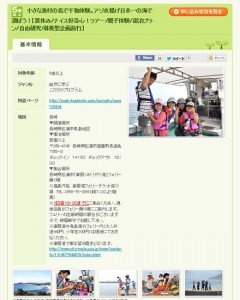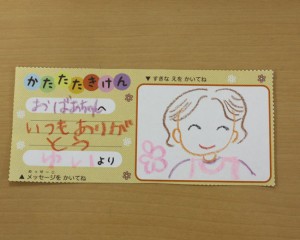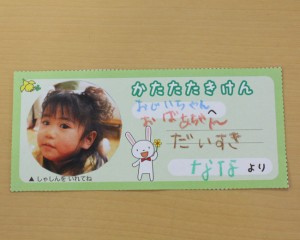JPIC読書アドバイザーの大橋悦子さんに
年長児におすすめの絵本の読み方、選び方について
お伺いしています。
最終回の今回は、
5歳児、6歳児にぴったりな絵本5冊を
ご紹介いただきます!
●幼児が主人公の2冊
大橋 「まずは1冊目。
『いちねんせい』 (谷川俊太郎/和田誠/小学館)
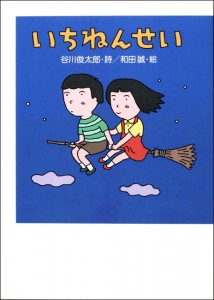
この詩集はお子さんと一緒に大きな声でお読みください。
すると…… 楽しい! とにかく楽しいのです。
リズミカルで愉快な響きを持った言葉が並ぶこの詩集は、
新しい言葉との出会いもたくさんあり、
言葉に対する感性が磨かれます。
小学校への期待が高まる内容が多い点も、この時期にピッタリ。
読めば、最後には必ず笑顔になってしまう不思議な詩集です。
絵本に収められた全ての詩を
暗唱してしまう子も珍しくありません。
2冊目は
『けんかのきもち』 (柴田愛子/伊藤秀男/ポプラ社)
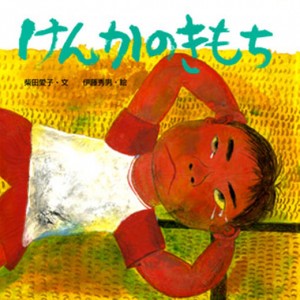
男の子なら誰でも経験のある友だちとの喧嘩。
でも、喧嘩は終わっても、
喧嘩の気持ちがすぐに収まるとは限りません。
そんな喧嘩の後の心と体の様子が
迫力のある絵で描かれています。
「こんどはきっとボクがかつ」なんてセリフ、
男だねえ、泣かせるねえ!
ということで、お父さん、読み聞かせの出番ですよ。
幼い頃のお父さんの経験などもお話し下さい。
そんな絵本を通じた親子のコミュニケーションが
とても大事な時期なのですから」
●変化球系の絵本で、共に笑い、驚こう!
大橋 「3冊目は脱力系絵本。
『キャベツくんのにちようび』 (長新太/文研出版)
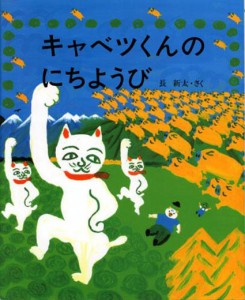
怪しげな招き猫の招きに応じて、後をついていくと、
ビックリするものが次々に登場します。
そのハチャメチャなストーリーに腹を立て、
ツッコミをいれるのは、無粋!
まさにその部分こそが、
ナンセンス絵本の魅力そのものなのですから。
摩訶不思議な絵本というのは、
思考に対するムーブメントが詰まった絵本。
お子さんの想像力に大きな刺激を与えてくれそうです。
次は摩訶不思議なアイデア絵本。
『地球をほる』 (川端誠/BL出版)
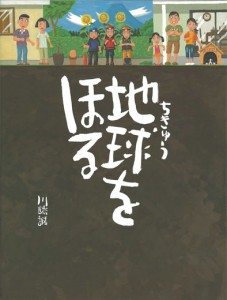
夏休みの旅行に、穴を掘って地球の裏側へ行ってみようと
計画したつよしとけんた。
高温の地球の中心を避けるため、
地球を斜めに掘ることを思いつき、
アメリカのケンタッキー州を目指します。
実はこのお話、この『地球を斜めに掘る』
というところがミソなのです。
掘り進むにつれて、少しずつ画面が回転していき、
アメリカへ到着した時には、
絵本をさかさまに持たなければ読めなくなっています!
読者へのサービス精神にあふれたとても洒落た絵本です。
最後は音楽に興味がもてそうな1冊。
『音楽ばんざい!』 (レ・シャ・プレ/石津ちひろ/ほるぷ出版)
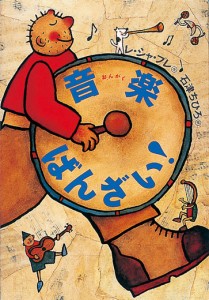
音楽は、どこからうまれたんだろう?
そんな素朴な疑問に答えながら、
音楽の歴史や世界の楽器のことが楽しくわかる絵本です。
よく見れば、不思議な生き物や怪しげな人たちが、
嬉しそうに楽器を弾いていますよ。
絵本の端から端まで楽しめるこの作品は
1996年ボローニャ児童図書展ノンフィクション部門最優秀賞を
受賞しています」
どの本も年長児が喜びそう!
ぜひ読んでみたいと思います。ありがとうございました!
関連記事はこちら
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓







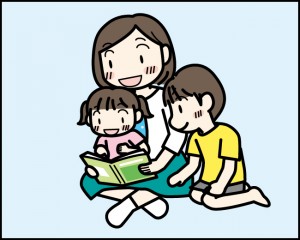
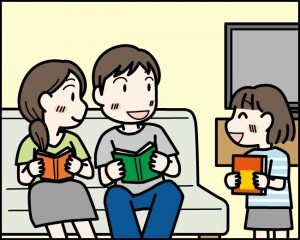
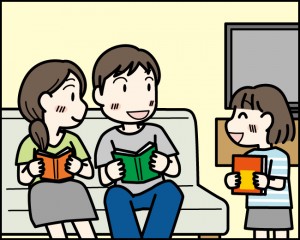















![☆子どもが自分で身を守る方法を身につけよう[2/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1210_img_01.jpg)

![☆無理なく文字や数を理解できるようにするには?[8/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/e603ac4e67fe8bcf379929b2ea3860aa-640x510.jpg)