上の子が下の子(弟・妹)をたたくなどの行動がよく見られるようであれば、その根本原因を探らなければなりません。NPO法人子育て学協会会長 山本直美さんにお話を伺いました。
●上の子が下の子をいじめる場合は…
山本 「兄弟ゲンカの根本原因は、その場で起こったことだけではなく、表面に見えていないことかもしれません。なぜ、弟・妹をいじめてしまうのか? その根本原因を探るためには、子どもの心の安定に欠かせない、次の3つの要素を見直す必要があります。
これは、兄弟ゲンカの解決法に限らず、子育ての悩みの解決法を探るときにも共通して言えることです。それでは、その3つの要素をご紹介します」
1.子どもの人間関係は安定している?
山本 「小学校に入学し、仲のいい友達と学校が別々になってしまったストレスから、下の子に当たることもあるようです。
また、友達とケンカをした、いじめられているなど、子どもの人間関係に問題があるケースもあります。子どもは環境の変化や人間関係で、大人が思う以上にストレスを抱えているものです。
大人でも、人間関係のストレスでイライラしてしまうことがあると思いますよね。気になることがあれば、お子さんに『この頃、ケンカが多いね。何かあったの?』と聞いてください。
お子さんは、親を心配させないように、はっきり答えてくれないこともあります。でも、それでいいのです。『親は自分のことをいつも気にかけてくれている』ということがわかり、安心感を持てます」
2.好きなことをする時間をとっている?
山本 「宿題、習い事など、小学校から帰ってきたあとにやることがたくさんあり、自分の自由な時間があまりない子もいます。絵を描く、絵本を読む、アニメを見る、電車を見る……など、お子さんが好きなこと、興味があることは何ですか? 好きなことに熱中する時間をどれぐらいとってあげているでしょうか?
お子さんの鬱積したストレスが発散できる“快”の時間を作ると、心が安定し、自然と兄弟仲もよくなります。
それは、大人にも同じことが言えます。家事や育児、仕事などから少し離れて好きなことを思いきりしたり、リラックスしたりするとホッとしますよね。お子さんにも、そんな時間を作ってあげてください」
3.生活リズムが崩れていないか?
山本 「イライラして下の子にあたってしまう原因は、生活リズムの乱れにあるのかもしれません。就寝時間が遅く、生活リズムが乱れていないか? 栄養バランスのいい食事をとっているか? おなかが空いているから機嫌が悪いのか? 1日の行動を見直してみてください。『○時までに就寝する』など、ルールを作って生活リズムを整えましょう。
以上の3つの要素を無視して、やみくもに兄弟ゲンカを止めたり、叱ったりしても、あまり効果はありません。この3つの要素をもとに、解決法を探ることが大切です。
お子さんが相手の気持ちを考え、行動できるように、サポートしてあげたいですね」
子どもの兄弟ゲンカの原因、イライラの根っこは何なのかを見極めることが大切なのですね。山本さん、ありがとうございました。



![上の子が弟・妹をいじめる……原因は何なの?[4/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/62631a792a747bb294e00fbf989848e6-800x510.jpg)

![★親野智可等の「今日から叱らないママ」第1回 [4/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/pixta_10776684_S.jpg)

![子どもの兄弟ゲンカは、どう仲裁すればいいの?[4/8]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/8de029079e6e761a16250ae2d0dfedec-659x510.jpg)

![兄弟ゲンカを止めるときに言ってはいけないことは?[4/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/746b75aa9138a27cce0da5315f51f5ed-716x510.jpg)

![お茶、お菓子は必要? 家庭訪問の最低限のマナー[4/7]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/739774ae02c7ea851fbf7abaa5f1e669.jpg)


![★新連載コラム 親野智可等の「今日から叱らないママ」[4/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/oyano-513x510.jpg)

![デコ弁『チューリップのデコパーツ』の作り方[4/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/127-825x510.jpg)






![★夏休み明けから学年末まで学校の1年を大公開![4/3]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/08f15fe991f76cda04fbbdae9347255b.jpg)

![★1学期から夏休みまで、学校の1年を大公開![4/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/bb41db52e83af1d4d2aa682bcd46914e-480x510.jpg)

![★給食から帰りの会まで、学校の1日を大公開![4/1]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/52e18d32d7dae0212a10c4fdba1aeae2-640x510.jpg)

![★登校から休み時間まで、学校の1日を大公開![3/31]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/08/88f530fec61eda4b47537866d2366083-640x510.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第43回 [3/30]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_27.jpg)
![☆子育てが上手くいかず、自分を責めていませんか?[3/27]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1238_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第42回 [3/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_26.jpg)
![★口答えで、乱暴な言葉を使うようになってきた![3/25]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1237_img_01.jpg)

![★素直に言うことを聞けない子どもにイラッ[3/24]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1236_img_01.jpg)

![お花見弁当『桜デコパーツ』の作り方[3/20]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1234_img_01.jpg)





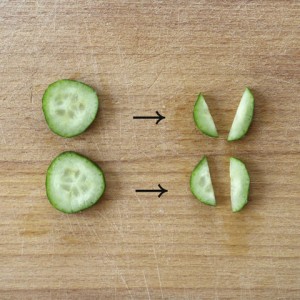


![無難なスーツを入学式バージョンにアレンジ[3/18]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1232_img_01-429x510.jpg)


![入学式のスーツ、1回きりにしないためには?[3/17]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1231_img_01.jpg)




![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第41回 [3/16]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_25.jpg)
![親の「伝え方」ひとつで、子どもは変わる! 動く![3/11]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1227_img_01.jpg)

![☆子どもの「やる気」を下げるNGワード[3/12]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1228_img_01.jpg)

![「インタビューごっこ」で子どものやる気アップ![3/13]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1229_img_01.jpg)

![子どもが「親の話を聞かない」のは、なぜなの?[3/10]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1226_img_01.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第40回 [3/9]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_24.jpg)
![デコ弁『みつばちデコパーツ』の作り方[3/6]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/1224_img_01.jpg)











![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第39回 [3/2]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_23.jpg)

![勉強大好き&学力アップ「親野智可等のママゼミ」第38回 [2/23]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/09/image.php_22.jpg)

