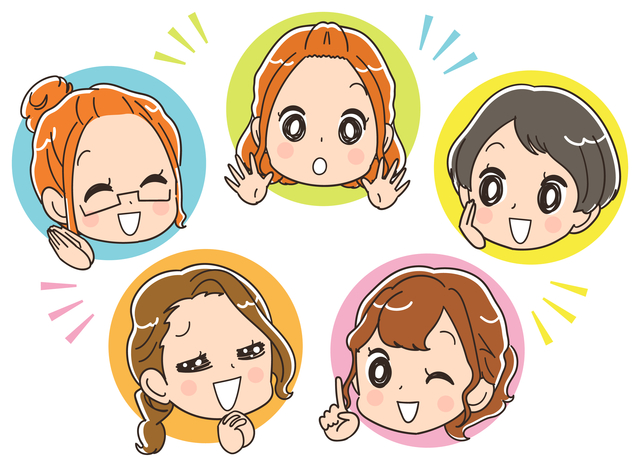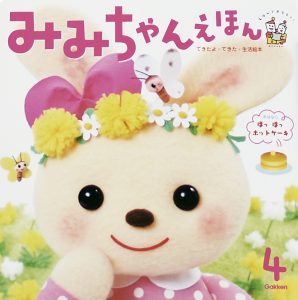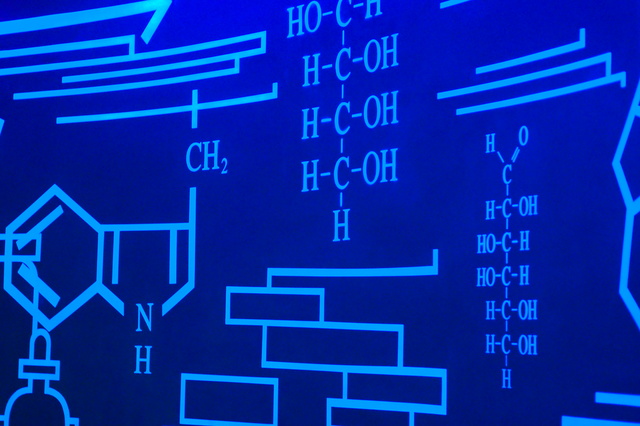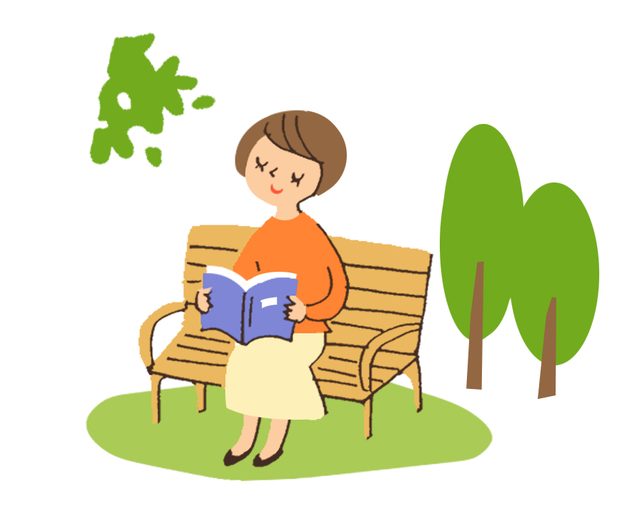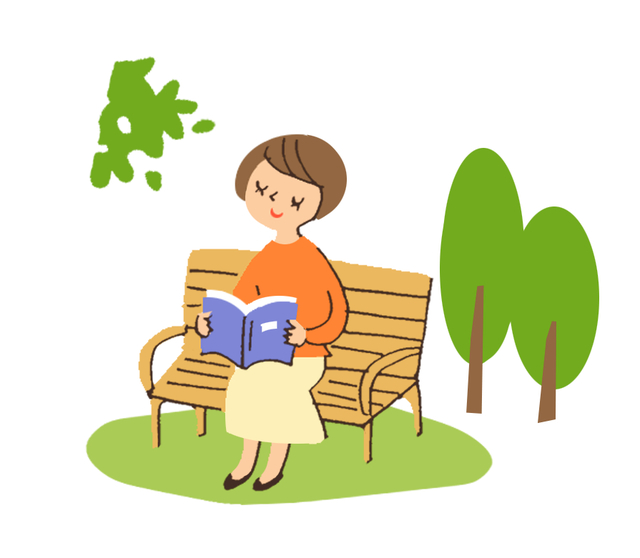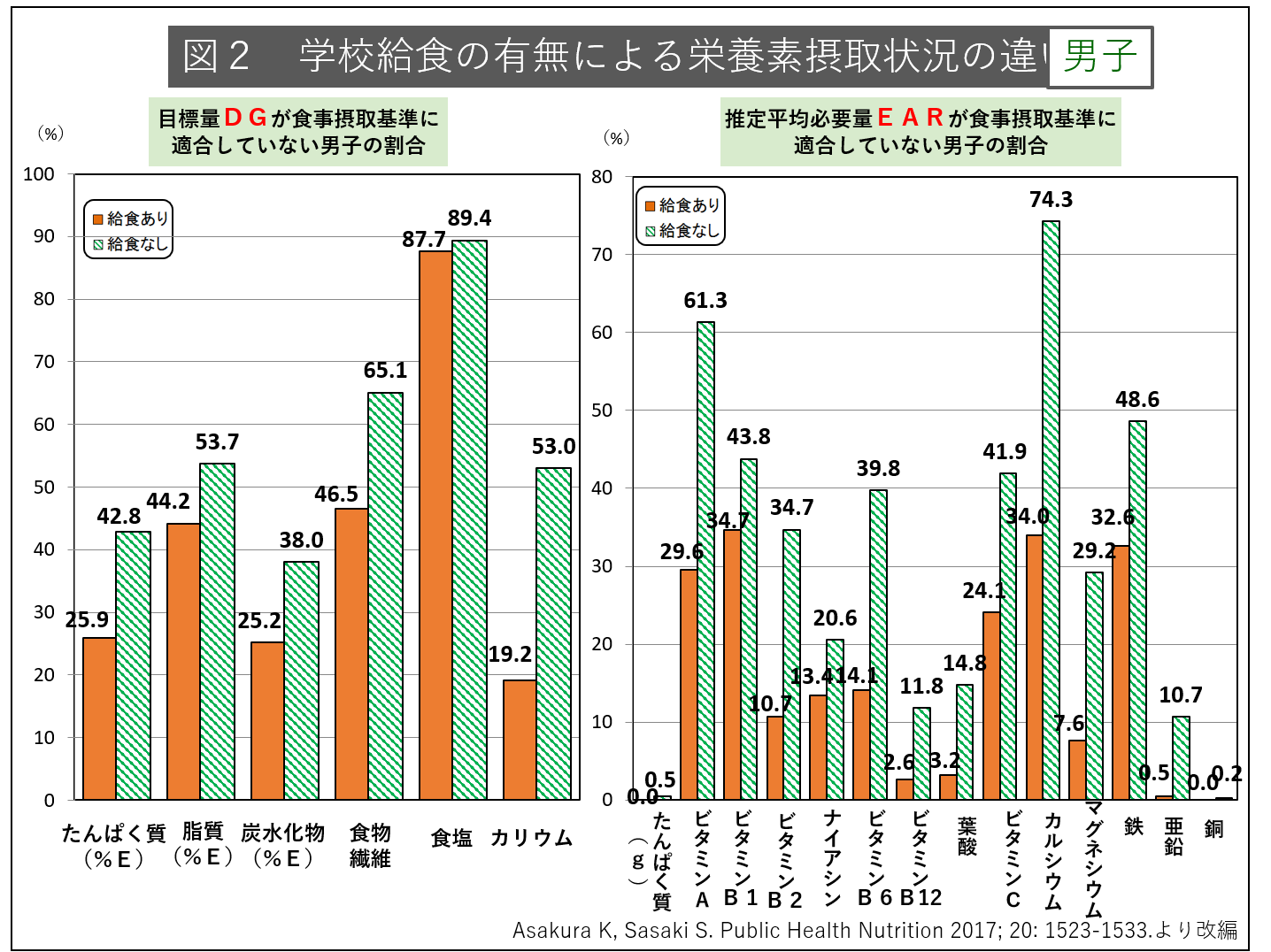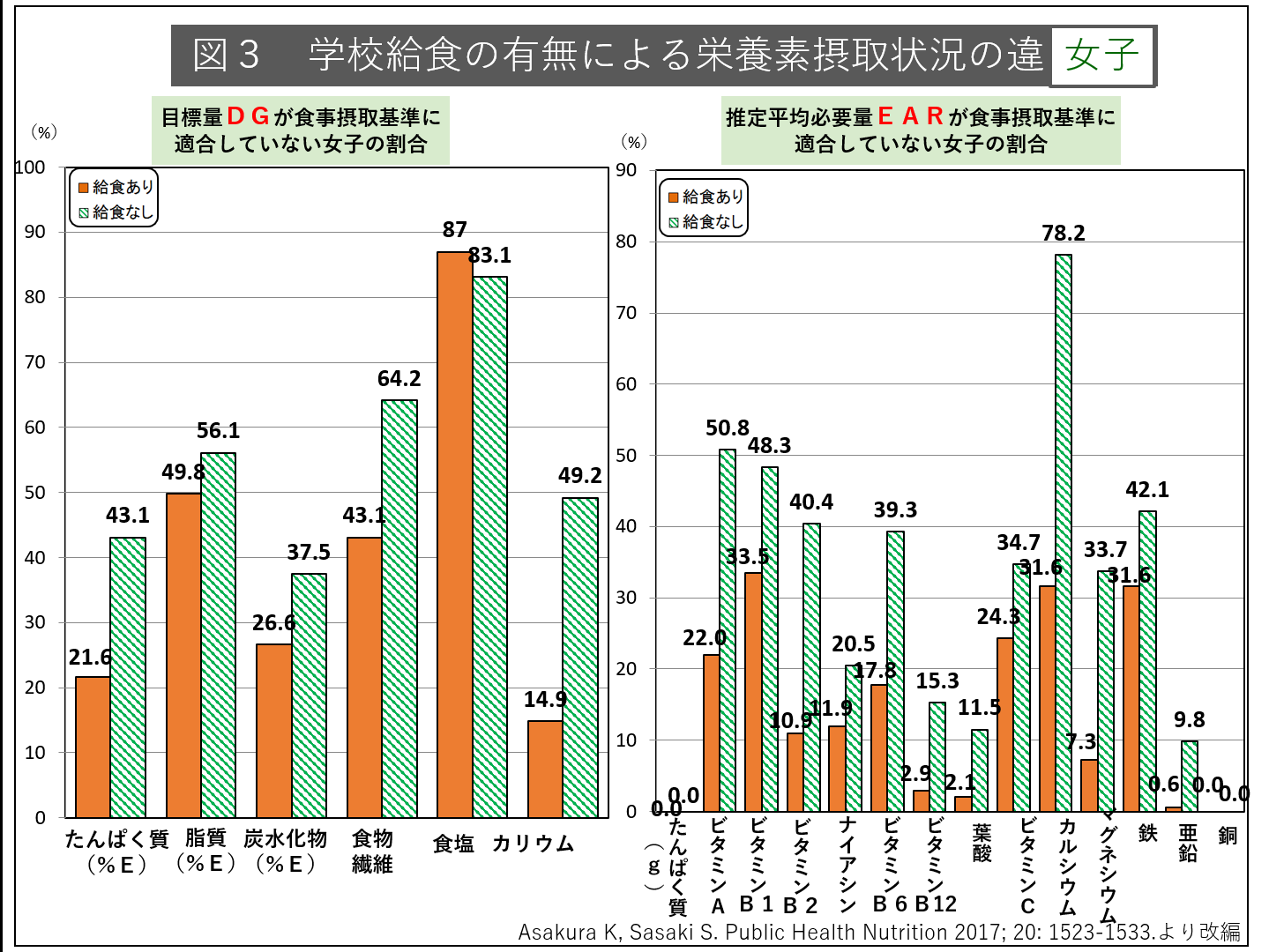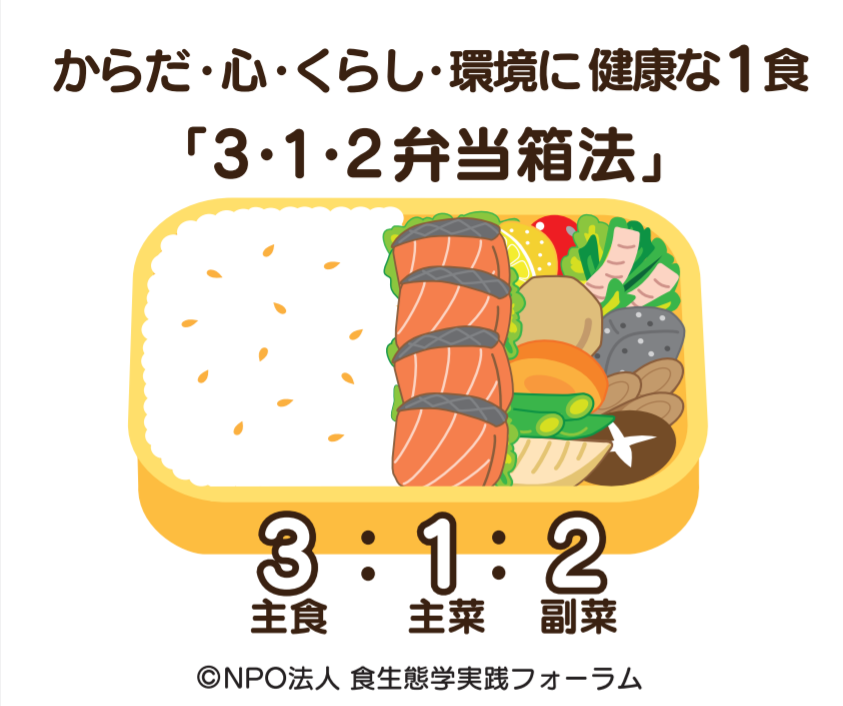(画像提供:土屋鞄製造所)
さまざまな種類があるランドセル。それぞれにどんな機能や特徴があり、どんな点を重視してランドセル選びをすればいいのでしょうか。そこで、ランドセルの主要メーカーに直撃取材。メーカーごとの発売時期、イチオシなどを詳しく教えてもらいました。第1回は土屋鞄製造所です。
(※ 記事内の商品価格は、すべて5/8現在のものです)
【土屋鞄製造所のランドセルのポイント】
・素材
牛革を中心に、コードバンを使った高級ライン、人工皮革を使ったものも。
・重さ
牛革は1,390g前後(素材によって異なる)
・カラー
男の子は黒、女の子は赤ピンク系が人気
・販売時期
店舗、オンラインショップともに4月10日より販売開始
・ポイント
☆高学年になっても似合う、シンプルなデザインとカラー
☆職人がひとつひとつ手作業で製造!
☆テキスタイルデザイナーとコラボしたおしゃれなデザインも
【男の子人気NO.1】
牛革アンティークモデル(カラー:黒)

(画像提供:土屋鞄製造所)
77,000円(税込)
シックなブラックカラーが不動の人気。アンティークモデルは、ベージュのステッチ、シックな金具が特徴。
【女の子人気NO.1】
牛革ベーシックカラー(カラー:赤×さくら)

(画像提供:土屋鞄製造所)
70,000円(税込)
表面はつややかな赤、肩ベルトと背当て、内装にはさくら色を使用したキュートなデザイン。
【今年のイチオシ!】
牛革プレミアムカラー(カラー:アッシュブルー)

(画像提供:土屋鞄製造所)
75,000円(税込)
今年の新色アッシュブルー。
●負荷がかかる部分は手縫い。職人手作りのランドセル
「工房系」ランドセルとして大人気の土屋鞄製造所のランドセル。現在は大人向けの革鞄も多く作られていますが、もともとは、下町のランドセル工房としてスタートしたそう。丁寧なランドセル作りには定評があります。
「大切にしているのは、6年間安心して使える丈夫さ。職人の手作りにより、150以上あるパーツの細かいところにもこだわり、上質で美しいランドセルを目指しています。大きな負担がかかりやすい肩ベルトの付け根などは、職人が手縫いをしており、太い糸でより頑丈に仕上げています。
また、飽きのこないシンプルなデザインも特長。水色やラベンダー、オレンジなどのカラフルなカラーも、デザイナーがひとつひとつ吟味して選んだ、上品な色合いです。黒や赤などの定番カラーも根強い人気です」(土屋鞄製造所 広報担当)
●今年も昨年と同時期の4月に販売が開始
その他、ランドセルやランドセル販売についての特徴は?
「昨年から、A4フラットファイルも対応のサイズになりました。学校でA4フラットファイルを使用する方にも、安心してお選びいただけます。
また、販売のスタートは4月10日から。ランドセルはじっくりと時間をかけて選びたいという親御さんの思いから、検討時期が年々早まっています。2020年入学用ランドセルについては、ご家族で納得いくまでお選びいただけるよう、完売製品を出さない期間をもうけています。注文受付開始から5月14日までは『コードバン つや有り仕上げ』『ヌメ革 ランドセル』を除き、全製品売り切れを気にせずにご注文いただけます」(同)
シンプルで丈夫なランドセルの特徴はそのままに、白熱するラン活事情への対応も行い、さらに購入しやすくなった土屋鞄のランドセル。天然皮革の風合い、背負い心地を体感するためにも「ぜひ店舗に足を運んでください」とのこと。西新井本店、軽井澤工房店では、併設された工房でランドセルを作っている様子を見学することもできます。また、4月13日~5月12日まで、週末を中心に店舗から遠い全国22か所で出張店舗も開催します。
(取材・執筆:野々山幸)