
秋が深まってきました。年長さんにとっては、園生活最後の秋。園のお友達と過ごす月も残りわずかです。芋掘り遠足や発表会、ふだんの遊びの中でも力をあわせていっしょに何かできたら、素敵な思い出になりそうですね。みんなで力をあわせたくなる絵本を紹介します。
ひとりひとりの力が大切!『あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま』
『あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま』(イ・ヨンギョン文・絵、かみやにじ訳)は、縫い物がとても上手な、頭に赤い手ぬぐいをかぶっている奥さんと、その7つの道具のお話です。「7にんのなかま」は7つの道具のこと。奥さんの部屋にはいつも、ものさし、はさみ、はり、いと、ゆびぬき、のしごて、ひのしという「7にん」がいました。
ある日、奥さんがうたた寝をしているすきに、ものさしふじんが「うちの奥さんがお針が上手なのは、なんといってもわたくしがいるからですわ」「いちばんだいじなのは、このわたくしですよ!」と主張をはじめたことから、大騒ぎがはじまります。物差しがないと寸法は測れないけれど、はさみおじょうさんがいないと布は切れないし、はりむすめがいないと針で布を縫い合わせることもできません。いとねえさんも、ゆびぬきばあちゃんも、のしごとおとめも、ひのしねえやも、みんな口々に、我こそはいちばん大切だといって争います。目をさました奥さんは、腹を立てて7つの道具を裁縫箱にほうりこんでしまいますが……?
表情ゆたかで味わいのある絵が魅力の、韓国の絵本。7つの道具をあらわす、むすめさんたちの口げんかはかわいらしく、声に出してせりふを読むのが楽しい絵本です。7つはそれぞれ自慢できる能力をもっているけれど、全員そろわなければりっぱな針仕事はできないし、力をあわせなければ一枚の洋服は作れないのだ、と子どもにわかりやすく教えてくれます。
「すまなかったね。おまえたち、ひとりひとりが、みんなたいせつだってことをわすれていたよ」そう奥さんにいわれて、照れくさそうに笑う「7にんのなかま」の場面は見どころです。お話の最後に「7にんのなかまがそろったよ」とうたいあげる素敵な詩がありますよ。歌うようにリズミカルに読んでみてくださいね。
でっかい長いお芋、折らずに掘り出せるかな?『14ひきのやまいも』
『14ひきのやまいも』(いわむらかずお作)は、子どもたちに大人気のロングセラー、14ひきシリーズの中の1冊。「おとうさん おかあさん おじいさん おばあさん そして きょうだい 10ぴき。ぼくらは みんなで 14ひき かぞく。」このおなじみの言葉からはじまります。いつも一家そろって「力をあわせる」姿が描かれる14ひきシリーズですが、中でもこの本は、特別! だって、でっかい長ーいお芋をひっぱって地中から掘り出すんですから。
秋の実りがいっぱいの山の中を、そろって出かける14ひき。木の実、見つけた。草の実、見つけた。収穫物はいっぱいです。その中でもみんなの知恵と力が必要なのは、山芋掘り。みんなで落ち葉をどかして、ザックザック、シャベルで土を掘ります。山芋が土の中から顔を出しましたよ。さて、山芋はどれくらい深いところまでのびているのかな……?
折らないようにまわりの土をかきだして、最後はみんなでつなひき! 力をあわせて、でっかい山芋を、えいさ、えいさとひっぱります。とうとうひっぱりあげた、どろんこ山芋。どろんこ14ひきの誇らしそうな顔。竹を組んだおみこしに山芋をのせ、わっしょい、わっしょいとかついで帰って、おいしい夕ご飯のはじまりです。
力持ちは力持ちらしく、小さい子は小さい子らしく、みんなそれぞれできることを精一杯がんばるねずみたちの姿は、きっと子どもに何かをおしえてくれるのではないでしょうか。最後に描かれる、食卓を囲む14ひきの、ほっとするようなあたたかい食事のシーンは「いつものかけがえのない時間」を伝えます。がんばったあとのごはんやおやつは最高ですね。「みんなでがんばった!」「みんなでやったね」という経験が、園生活の思い出になりますように。
毎週木曜にメルマガ発信中!
ご登録はこちらから↓
ツイッターもやっています!
フォローはこちらから↓












![先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.2]後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/10/5ea8308e31d781198cc388946fe4e228.jpg)

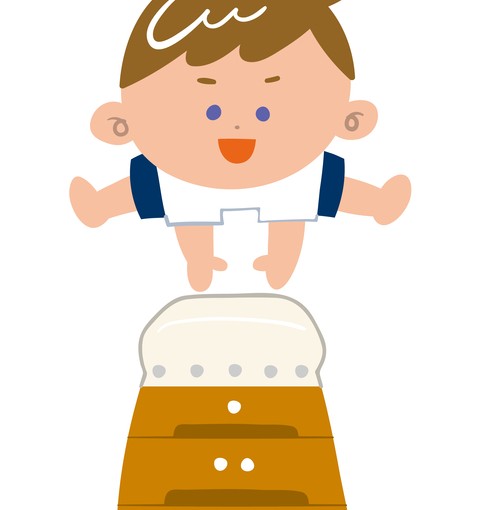

![家庭でできる年長児の入学準備[その5]「右」「左」の教え方](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/10/3dd9ba3910709b50e6026fb537d6c6b9.jpg)




![家庭でできる年長児の入学準備[その4]時計の読み方 後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/3db732cfbe929713fabf50464785f97f.jpg)

![家庭でできる年長児の入学準備[その3]時計の読み方 前編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/08/fc59c303a1493582778762e5ece1e433.jpg)









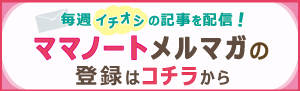


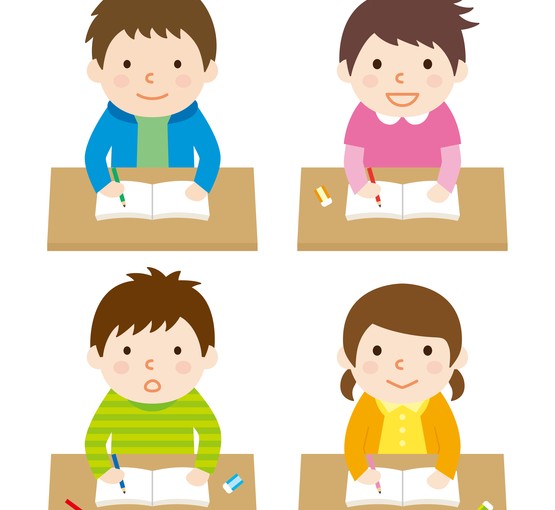
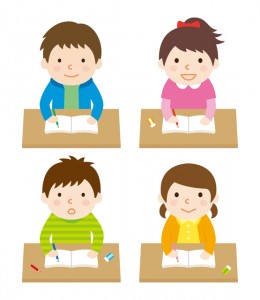


![「学校に行きたくない」って言われたら?[第3回]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/06/ae11603ca3a15168d022bcff211996a5.jpg)





![「学校に行きたくない」って言われたら?[第2回]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/06/22f94f8a4b72798b6bf3431432c3fb53.jpg)

![「学校に行きたくない」って言われたら?[第1回]](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2015/06/6052baa23fbc254eb42cd4c22c0ad3e5.jpg)













![家庭でできる年長児の入学準備[その2]ひらがなの練習 後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/ec5f59bec37bb8bde861d58dc1c9a846.jpg)



![家庭でできる年長児の入学準備[その1]ひらがなの練習 前編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2016/09/1940027f0193d680bd547068ff1eef67.jpg)

![先輩ママに聞く、「小1の壁」ってどんなもの?[Vol.1]後編](https://mamanote.jp/wps/wp-content/uploads/2017/08/e20bb02d018a5b2f0c57bde917c3f52f.jpg)


